こんにちは、garesuです。
毎年冬になると、手足がじんわり冷えてつらい…
布団に入っても足先だけがいつまでも温まらない‥‥
そんな“冷えの季節の悩み”は、実は 腸 と深く関係しています。
腸が冷えると、全身の血流が落ち、
体も心も“エネルギーが回らない状態”になりやすくなります。
そこで役立つのが、
腸からやさしく温めてくれる発酵食品の力。
無理に長湯をしなくても、
特別な運動をしなくても、
毎日の食卓と小さな習慣で、身体はふわっと温まりはじめます。
今日は、寒がりの私自身が実践している“日々の小さな温活”と、
すぐ試せる発酵の取り入れ方をお届けしますね。

冷えは「腸」からやってくる
冷えやすい体質の裏側には、“腸の温度”が深く関わっています。
腸は、体の中心で熱をつくり出す臓器。
この腸が冷えてしまうと、
- 血流が滞る
- 手足の末端まで温かさが届かない
- 自律神経のバランスが乱れる
という悪循環に。
とくに女性は筋肉量が少ないため、体の中心を温める力が弱く、
季節の変わり目やストレスで“冷え腸”になりやすいのです。
冷え腸を引き起こす4つの要因
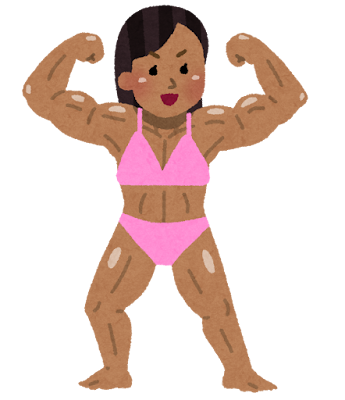
- 筋肉量が少なく発熱しにくい
- ホルモン変化で血流が乱れやすい
- 冷たい飲み物・スイーツ習慣が影響しやすい
- ストレスで腸の動きが鈍くなる
「体は冷えているけど、原因がわからない」という人ほど、
まず“腸を温める”と楽になります。
発酵食品が温活を助けてくれる理由
「食べるだけなのに、なぜ体が温まるの?」
その秘密は、発酵の過程で生まれる“菌の働き”にあります。
腸内の善玉菌が増えて、腸が動き出す
発酵食品に含まれる乳酸菌や麹菌は、腸を刺激して動きをサポート。
腸が動くと、体の中心“コア”の温度が上がりやすくなります。

発酵による酵素・アミノ酸が血流をサポート
発酵の過程で生まれる酵素やアミノ酸には、
血流を促して「めぐる体」に整える働きがあります。
結果として、
足先・指先までじんわり温まる体へ。
あたたかい発酵汁物と相性が良い

味噌汁、甘酒、塩麹スープなど、
“温め+発酵”の組み合わせは温活に最適。
温かい状態で取り入れるだけで、腸の巡りがふんわり整います。
日常でできる“やさしい温活習慣”
ここからは、garesuが実践している習慣も織り交ぜて、
今日から取り入れられる温活をご紹介しますね。
朝いちばん、肩をゆっくり回すだけ
「両肩をゆっくり回す」
これは、じつは最高の温活です。
肩周りの血管が広がり、体の中心が温まりやすくなります。
- 朝の目覚めに3〜5回
- 深呼吸しながらゆっくり
- 背中までじんわり温まる実感が出やすい

醤油麹・塩麹で“ぽかぽか簡単ごはん”
garesuが手作りしている 醤油麹 は温活に相性抜群です。

- しょうが × 醤油麹のお湯割り
- 醤油麹 × 卵かけご飯(体温が上がりやすい)
- 塩麹 × 野菜スープ
麹の酵素は腸をやさしく刺激し、温活の土台をつくります。
発酵食品は「冷やさず」に食べる
納豆、ヨーグルト、キムチ……
冷蔵庫から出したてだと、腸が冷えてしまうことも。
おすすめは:
- ヨーグルト:ぬるい白湯と一緒に
- 納豆:常温に10〜15分置く
- キムチ:スープや炒め物で“温活アレンジ”

「発酵 × 温かい」この組み合わせが体質改善の鍵です。
サウナで“短時間あたため”もOK
garesuのように長湯が苦手な方は、サウナの“短時間温活”がぴったり。
- 5〜8分だけ入る
- 水分をこまめに
- 湯冷めしないようにすぐ保湿・白湯
無理のない、心地よい範囲で続けるのがコツです。
あたたまる発酵ミニレシピ
しょうが甘酒(基本の温活ドリンク)
材料
- 甘酒(米麹) … 150ml
- すりおろし生姜 … 少々
- シナモン(お好みで)
作り方
- 甘酒をゆっくり温める(沸騰はNG)
- 生姜を加える
- カップに注ぎ、シナモンをひとふり
体の内側からふわっと温まります。
塩麹のぽかぽか野菜スープ
材料
- 玉ねぎ … 1/4個
- 水 … 400ml
- 生姜 … 小さじ1
- 塩麹 … 大さじ1
- オリーブオイル … 小さじ1
作り方
- 玉ねぎを炒める
- 水・生姜を加え4分煮る
- 火を止めて塩麹を入れる
麹のやさしい甘みが広がり、ホッとする味に仕上がります。
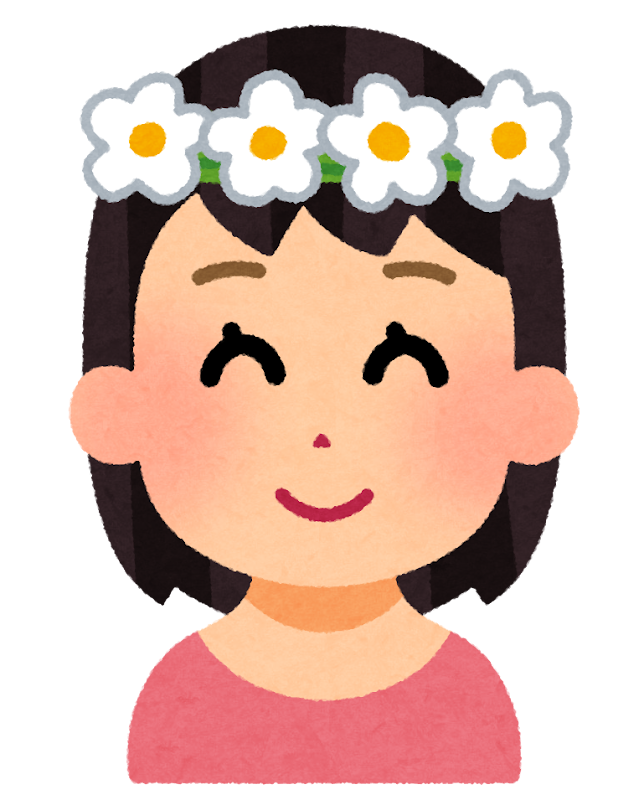
いかがでしたか?
冷えがやわらぐと、
体だけではなく、心の緊張までゆっくりほどけていきます。
季節の寒さや忙しさに負けない、
“やさしい温活”をあなたのペースで続けてみてくださいね。


