こんにちは、garesuです。
日本酒の「原料」からの話になります。
日本酒の原料はとってもシンプルです。
シンプルだからこそ質が重要になってきます。
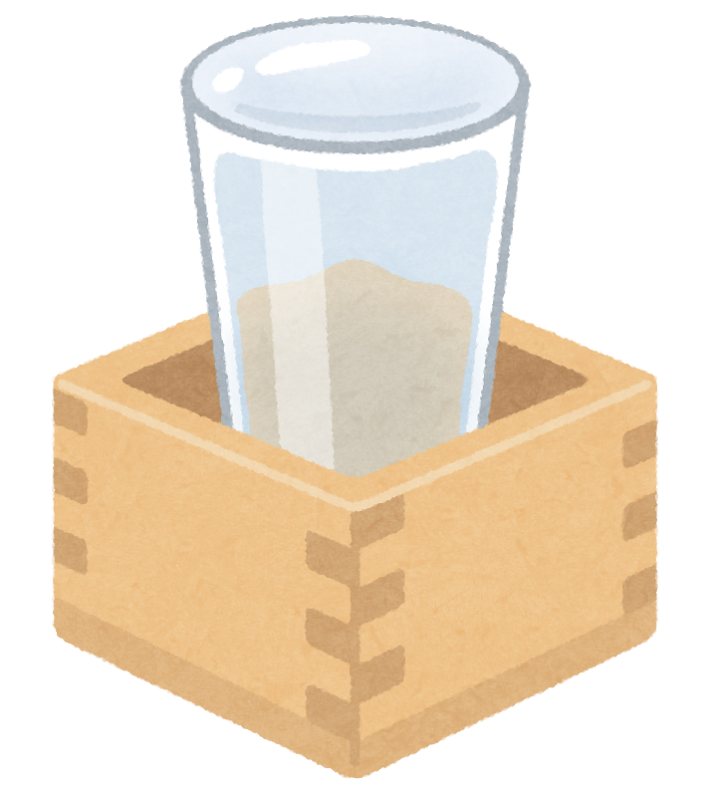
原料
酒づくりの原料は米、水、酵母です。
米
酒づくり用の米は、酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)という品種が使用されます。
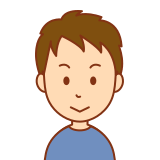
酒米(さかまい)、心白米(しんぱくまい)とも呼ばれます。
食用米に比べて粒がひと回り大きく、中心部分のデンプン質に隙間があり、粗く「心白」と呼ばれる不透明な部分があるのが特徴です。
タンパク質の含有量は少ないです。

心白のある米は、精米してもくだけにくく蒸した時に外が硬く中が柔らかい外硬内軟(がいこうないなん)と呼ばれる状態になりやすい性質があります。
この状態だと麹菌が米の内部まで菌糸を伸ばしやすく、仕込んだときに米が溶けやすくなるため、酒造りには適しています。
代表的な酒米には、「山田錦」「五百万石」「雄町」などがあります。
水
水は仕込みだけではなく、洗米や酒瓶の洗浄にも使われるため日本酒の産地は良質な水が豊富にあることが条件になっています。
醸造に使用する水の品質は日本酒の風味に大きく影響します。軟水や硬水の違いにより、酒の口当たりや味わいが変わります。

酵母
酵母は糖をアルコールと二酸化炭素に分解する微生物で、日本酒の発酵過程で不可欠です。酵母の種類によっても香りや風味が変わります。
日本酒づくりに使われる清酒酵母はアルコール耐性や発酵力が強く17〜18度というアルコール度数になるまでアルコールを生成して日本酒独特の香気成分を生産します。
日本酒の醸造工程
日本酒の醸造工程はとても複雑です。
基本的な流れをお伝えしますね。
原料処理
玄米を精米して雑味の原因となるタンパク質や脂質を取り除きます。
※精米歩合はお酒の銘柄によって異なります。
1 精米後に米を洗います(洗米)が、そのときにも米の表面が削られます。このことを二次精米ともいわれます。
2 洗った米は水に漬けて(浸漬)蒸しやすい状態にします。
3 水を吸った米を甑(こしき)を使い蒸し、その後冷却します。
蒸した米は麹や酒母づくり、もろみの仕込みに使われます。
麹づくり(製麹)
製麹‥せいきくと読みます
1 麹の繁殖に適した温度まで冷まし蒸した米を麹室(こうじむろ)へ運ぶ。
2 種麹(麹菌の胞子)を振りかけて繁殖させます。
米麹の種麹は「ニホンコウジカビ」とよぶ黄麹菌です。
製麹とよばれる米麹づくりがとても重要な工程といわれます。
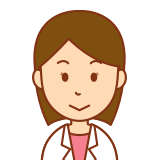
日本酒づくりには、「一麹、二酛(もと)、三造り」という言葉があり最も重要な工程です!
一麹づくり、二酒母(酛)づくり、三醪(もろみ)づくり
酒母(酛)づくり・仕込み
1 蒸した米と米麹を混ぜ合わせて、水と酵母を加え培養して酒母をつくります。
※酒母は酛(もと)ともいいます。酒の元になります。
2 酒母ができたら三段階に分けた仕込み、三段仕込みという方法で蒸した米と米麹と水を3回に分けて酒母に加えます。
雑菌の繁殖を抑えつつ酵母の働きを高めます。
醪(もろみ)づくりでは、麹菌によるデンプンの糖化と、酵母によるアルコール発酵が同時に進みます。これは並行複発酵といい三段仕込みとともに日本酒特有の醸造技術として知られています。
三段仕込みの工程表
| 仕込み段階 | 時期 | 追加するもの | 発酵状態・目的 |
|---|---|---|---|
| 酒母(しゅぼ) | 初日 | 酒母(発酵の元)を使用 | 強い酵母を増殖させ、発酵の準備を整える |
| 初添(はつぞえ) | 2日目 | 蒸米、米麹、水 | 発酵をゆっくり開始させるため、少量の材料を加える。初期の発酵促進。 |
| 踊り(おどり) | 3日目 | なし(発酵の調整期間) | 「踊り」とは、材料を加えずに発酵が自然に進む状態。酵母の活性を高める目的。 |
| 仲添(なかぞえ) | 4日目 | 蒸米、米麹、水(初添より多め) | 酵母の活動が活発になる。量を増やして発酵の進行を強化。 |
| 留添(とめぞえ) | 5日目 | 蒸米、米麹、水(最大量) | 最終的に大量の材料を加え、もろみの発酵を最大化する。アルコール生成が進む。 |
| 発酵期間 | 約20~30日 | もろみ全体 | 発酵を続け、アルコール度数と風味が成熟。温度管理が重要。 |
上槽(じょうそう)・火入れ・瓶づめ
上槽
もろみの発酵が終了した後、その液体を絞り出し、日本酒(清酒)と固形物(酒粕)に分離する工程です。この過程で、もろみを絞り、液体部分が最終的な日本酒になります。
方法:上槽にはいくつかの方法があります。
ヤブタ式(機械圧搾):もろみをフィルタープレス機にかけ、圧力をかけて酒を搾り出す一般的な方法です。
袋吊り:もろみを布袋に入れ、自然な圧力で時間をかけて液体を滴らせる伝統的な方法です。特に高級な日本酒で用いられます。
舟搾り(ふなしぼり):木製または金属製の槽(ふね)で搾る方法で、これも伝統的な手法の一つです。
酒粕:搾った後に残る固形物は「酒粕」と呼ばれ、食材としても利用されます。
火入れ
日本酒を瓶詰め前に加熱処理する工程で、酵母や酵素の活動を止め、酒の品質を安定させるために行います。この処理によって、日本酒の味が変わることなく保存が可能となり、雑菌の繁殖を防ぎます。
温度と方法:火入れは通常60℃〜65℃程度で行います。
- 上槽後の火入れ:絞った後の清酒に火入れを行い、品質を安定させます。
- 瓶詰め前の火入れ:貯蔵熟成後、瓶詰め直前に再度火入れを行うことがあります。
- 火入れを1回しかしない場合や、全く行わない「生酒」もあります(生酒はフレッシュでフルーティーな味わいが特徴)。
瓶詰め
瓶詰めは、火入れや貯蔵を終えた日本酒を瓶に詰める最終段階です。
- 瓶詰め工程:
- 火入れ後、日本酒はタンクで一定期間貯蔵され、熟成させます。貯蔵期間により、酒の味わいや香りが変化し、まろやかさが増します。
- 貯蔵が完了した後、酒は再度濾過され、不純物を取り除きます。
- 必要に応じて再度火入れが行われ、瓶詰めします。
- ラベル付けと出荷:瓶詰めが終わった後、各酒造のラベルが貼られ、出荷準備が完了します。ラベルには、酒の種類や精米歩合、アルコール度数などが記載されており、消費者がその日本酒の特徴を理解できるようになっています。

いかがでしたか?
次回は日本酒の味わい、効果をお伝えしますね。
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


