こんにちは、garesuです。
私たちの腸には、数百種類もの腸内細菌が住んでいて、健康を支える大切な働きをしています。
最近の研究では、「腸内環境」が心の状態にも深く関わっていることがわかってきました。
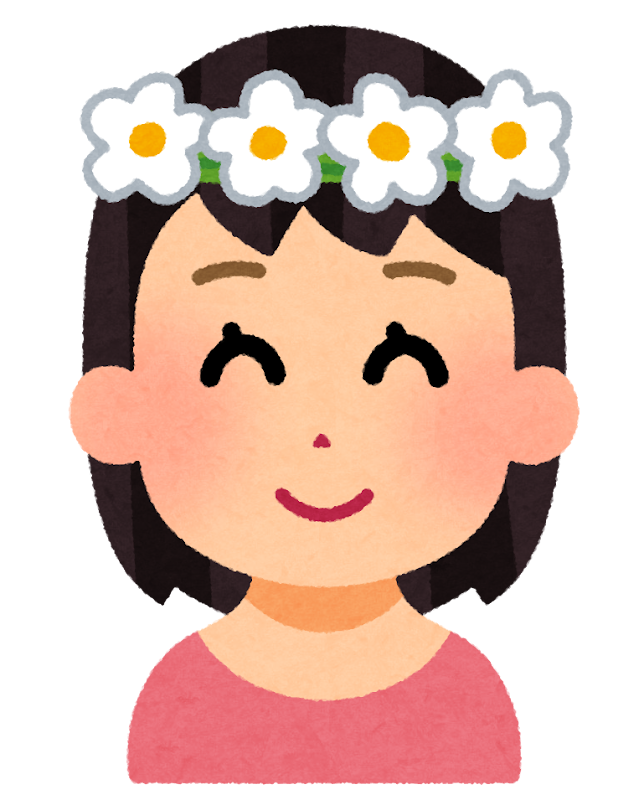
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、ストレスや感情と密接につながっています。
腸内環境が整うと、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの分泌が促され、気分が安定しやすくなるのです。
脳のはたらきにも腸内細菌が関係していることが明らかになっています。
腸と脳は心のパートナー
脳腸相関(のうちょうそうかん)とは?
脳腸相関(のうちょうそうかん)とは、脳と腸がたがいに影響し合っている関係性を指す言葉です。
たとえ話しではなく、実際に神経・ホルモン・免疫系などを通じて、脳と腸が密接なコミュニケーションを取っていることが科学的に確認されています。
何かの理由で強い緊張や不安を感じたときに急にお腹が痛くなってトイレに行きたくなった経験がある人は多いのではないでしょうか?
また、旅行先など慣れない環境で過ごしていると、便秘になりやすい人もいますよね。
これは、脳にストレスを受けたことで腸が反応して、蠕動(ぜんどう)運動が乱れているために起こる現象なのです。
どのように脳と腸はつながっているのか
・自律神経(特に迷走神経)
→ 脳と腸を直接つなぐ神経のルート。
腸の情報は迷走神経を通じて脳に伝えられ、逆に脳からも指令が届きます。

・ホルモンや神経伝達物質(セロトニンなど)
→ 実はセロトニンの約90%が腸で作られていて、心の安定や気分の調整に関与しています。
・免疫系
→ 腸内には全身の免疫細胞の7割以上が集まり、体調やストレス反応にも影響を与えます。
どのような影響があるのか
ストレスを感じるとお腹が痛くなる
緊張すると便秘や下痢になりやすい
腸内環境が乱れるとイライラや不安が強くなる

こうした経験は、「脳腸相関」が働いている証拠なのです。
腸は 第2の脳
腸には、腸管神経系と呼ばれる、脳とは独立して働く神経ネットワークが存在しています。
この腸管神経系には、約1000億個が集まっていて、その数は脊髄とほぼ同じです。
つまり腸は、ただ食べ物を消化する器官ではなく、自ら考え、反応する能力を持つ“もうひとつの脳とも言えるのです。
※腸は人体の中で脳の次に多くの神経細胞が集まっている場所なのです。
例えば、外食で緊張したり、ストレスを感じるとお腹が痛くなることはありませんか?
これは、脳で感じたストレスが腸に伝わるだけでなく、腸自体が独自にその影響を受けて反応しているからです。
また、腸内ではセロトニンなどの神経伝達物質も作られており、私たちの「気分」や「感情の安定」にも深く関わっています。
つまり、腸は「消化器官」であると同時に、「心の状態を左右する器官」でもあるのです。
しかし、生命の歴史をさかのぼっていくと、先に誕生したのは腸であり、脳は腸から分離して発達してできた器官なのです。
例えば、クラゲやイソギンチャクなどの腔腸(こうちょう)動物には脳がありません。が、腸にある神経細胞の指令によって、栄養を取り込んで消化吸収することができます。
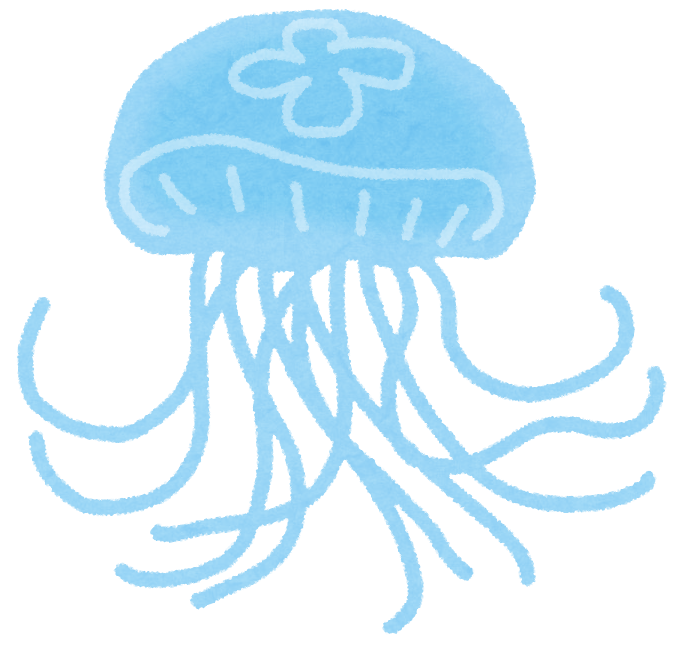
ヒトの場合も同様に、脳から命令を受けなくても、腸の神経細胞が自分が判断して蠕動運動や消化液の分泌を調整しています。
また、腐ったものや毒物が体内に入ったときに、胃から逆流させて吐き出したり、下痢の症状を起こして体外へ排出したりするのも腸の命令によるものといわれています。

腸が整うと心も整う
腸内環境とメンタルの不思議な関係
「なんとなく気分が晴れない…」そんなとき、実は腸内環境が影響しているかもしれません。
腸と脳は密接につながっていて、腸内細菌がつくり出す物質が、感情やストレス反応に関わる神経伝達物質に影響を与えることがわかっています。

腸内には数百兆個もの腸内細菌が存在し、これらは消化や免疫だけでなく、脳の働きにも影響を与えているのです。特に注目されているのが、腸内細菌がつくり出す神経伝達物質(セロトニンなど)や短鎖脂肪酸などの代謝物。
これらの物質が腸から脳にシグナルを送り、私たちの気分や感情、ストレス耐性に関わっていることが、近年の研究で明らかになっています。
性格は腸しだい? 腸内フローラと気質の不思議な関係
最近の研究で、腸内フローラが私たちの「性格」や「気質」にまで影響を与えている可能性があることが分かってきました。
何度もお伝えしますが、腸には、数百兆個にも及ぶ細菌がすみついていて、そのバランスが心の健康や感情のコントロールに関わる神経伝達物質の分泌に影響を与えています。
たとえば、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの約9割が腸でつくられているのをご存知でしょうか?
このセロトニンは、心の安定や前向きな思考を支える重要な物質。
つまり、腸内環境が乱れると気分が不安定になったり、逆に腸内細菌の状態が良いとストレスに強く、穏やかな性格になりやすいとも考えられているのです。
マウスの実験でも、腸内細菌を持たない無菌マウスに特定の腸内細菌を移植すると、行動パターンや反応が変化することが確認されていて、腸内フローラと性格・行動との関係は人間にも当てはまる可能性が高いと見られています。
もちろん、性格は腸内環境だけで決まるものではありませんが、腸を整えることが心の安定や前向きな気持ちを育てるための土台になることは間違いなさそうですね。
“しあわせ気分”は腸からやってくる?
脳に受けたストレスが腸に影響を及ぼすのとは逆に、
腸の状態が脳に影響を及ぼすことも研究で明らかになりつつあります。
神経伝達物質と感情の深い関係
私たちが「うれしい」「悲しい」「イライラする」と感じるのは、脳内で神経伝達物質と呼ばれる化学物質がはたらいているからです。
中でも有名なのが、セロトニンとドーパミン。
この2つは、心のバランスを保つうえでとても重要な役割を担っています。
セロトニン:「心の安定剤」
セロトニンは、不安や緊張を和らげ、気持ちを穏やかに保つ働きを持つ物質です。
ストレスに負けにくくしたり、睡眠のリズムを整えたりと、心の安定に欠かせない“幸せホルモン”とも呼ばれています。
驚くことに、セロトニンの約90%は腸でつくられているとされ、腸内環境が整っていることがその分泌に大きく関係しています。
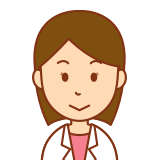
腸内のセロトニンの役割
腸内のセロトニンには蠕動運動をコントロールするはたらきがあります。
腸内でセロトニンが不足すると便秘になり、過剰になると下痢を引き起こします。
ドーパミン:「やる気スイッチ」
一方、ドーパミンは「快感」や「やる気」「達成感」などを感じるときに分泌される神経伝達物質です。
好きなことに熱中しているときや、目標を達成したときなどに多く分泌され、モチベーションを高める“快楽ホルモン”として知られています。
しかし、ドーパミンが過剰に出ると依存や衝動的な行動につながることもあるため、バランスが大切とされています。
腸内細菌がセロトニンのもとをつくる
セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、私たちの気分を安定させたり、睡眠リズムを整えたりする大切な神経伝達物質です。
このセロトニンの材料となるのが、5-ヒドロキシトリプトファン(5-HTP)という物質。
実は、この5-HTPをつくるプロセスには腸内細菌の働きが関わっています。
食事から摂った必須アミノ酸のトリプトファンは、腸内で腸内細菌の作用によって5-HTPに変換されます。
そしてこの5-HTPが、体内でセロトニンへと変化していくのです。
ここで重要なのがビタミンB6です。
ビタミンB6は、5-HTPをセロトニンへ変えるために必要な補酵素であり、不足するとこの変換がスムーズに進まなくなってしまいます。
腸内細菌がトリプトファンから5-HTPをつくり、ビタミンB6がその先のセロトニン合成をサポートするという、“腸と栄養と心”をつなぐ見えない連携プレーがあるのです。
腸内環境を整え、ビタミンB6を含む食品(バナナ、鮭、にんにくなど)を意識してとることで、心の健康もぐっと安定するかもしれませんね。

いかがでしたか?
私たちの心の状態が、実は腸の中で静かに支えられているなんて、ちょっと不思議でおもしろいですよね。
日々の食事や生活習慣を見直すことが、心の安定につながる!そう思うと、腸を大切にすることの意味が少し変わって見えてきます。
今日も腸をいたわりながら、自分の“ごきげん”を大事に過ごしていきたいですね。
次回は自律神経と腸についてお伝えしますね。
参考文献 「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 伝統的な和食と日本の発酵文化」 U-CAN


