こんにちは、garesuです。
「漬物」といってもたくさんの種類があります。
こちらではいくつかの漬物をお伝えしたいと思います。
麹漬け
糠漬けと同じくらい日本全体で食べられている漬物に麹漬けがあります。
米麹や塩、砂糖を混ぜて発酵させた漬け床に野菜などを漬けた発酵漬物。
三五八漬け(さごはちづけ)
福島県会津地方など東北地方を中心に古くから食べられている伝統的な発酵漬物です。
塩、米麹、米を3:5:8の割合にして漬け床をつくることから、この名前がつきました。
野菜のほかに肉や魚を漬け込むこともあり、漬けあがったものは焼いたり鍋料理に入れたりしても美味しいです。
塩麹とよばれる調味料は三五八漬けの漬け床が原型であるといわれています。
べったら漬け
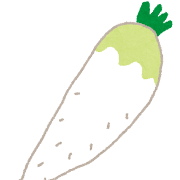
べったら漬けは東京名物として知られています。
大根を薄塩で下漬けをして、米、麹、砂糖を混ぜた漬け床で本漬けしたものです。
水分を多く含み、保存性は高くありません。
甘味のある味わいとポリポリとした歯触りが特徴です。
名前の由来は、漬け上がった大根がべたべたしていることからきています。(諸説あります。)
日本橋大伝馬町にある宝田恵比寿神社の界隈で毎月10日に開催される「べったら市」で販売されるのも有名です。
塩漬け
日本の漬物の中で最も古く、漬物の原点とも言えます。
もとは野菜の保存性を高める目的で塩漬けをしたところ、野菜に付着している乳酸菌と材料の糖類の作用で偶然発酵したことが始まりだと考えられています。
すぐき漬け
すぐき漬けは、京都の伝統的な漬物で、特に上賀茂地域で作られる乳酸発酵させたカブの漬物です。
上賀茂地区を中心に栽培されている酸茎菜(すぐきな)という根菜を、塩だけで漬け込み乳酸発酵させたもので、さわやかな酸味が特徴です。
酸茎菜の皮をむき、樽で漬け込みますがその際にてんびんを使う方法で重石をするという作り方も特徴的です。
1993年にすぐき漬けからラブレ菌とよばれる植物性乳酸菌が発見されたことで、健康に良い漬物として知られるようになりました。
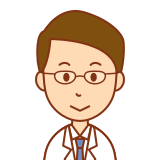
ラブレ菌は、正式には「植物性乳酸菌ラクトバチルス・ブレビスKB290」と呼ばれる乳酸菌の一種です。「すぐき漬け」から発見された菌株で、胃酸や胆汁に強く、生きたまま腸に届くことが特徴です。
ラブレ菌は、腸内環境を整え、便秘の改善や免疫力の向上に寄与するとされています。近年は、サプリメントや発酵食品に利用されており、健康効果が注目されています。
しば漬け
しば漬けは、京都の伝統的な漬物で、主にナスやキュウリ、シソの葉などを赤紫蘇とともに塩漬けにし、腐敗防止用の重石を乗せてしっかり空気を抜き、夏の高温を利用して乳酸発酵させて作られます。しその風味と発酵による酸味が特徴的です。
発酵をともなわないしば漬け風味の漬物と区別するために、最近は「生しば漬け」や「発酵しば漬け」と表記されることもあります。

粕漬け(糠漬け)
粕漬けは日本酒を作る際に出る酒粕や、みりんを作る際に出るみりん粕を使う発酵漬物です。
野菜、果実、魚類、肉類と色々な粕漬けが日本全国でその土地の食材を生かしたものがつくられています。
発酵によってできたうま味成分や香気成分が素材のおいしさを引き立たせます。また、魚の生臭さを消す効果もあります。
奈良漬
奈良漬は、奈良発祥の伝統的な漬物で、主にウリやキュウリ、ナスなどの野菜を酒粕に漬け込んで作られます。
粕漬けの代名詞ともいえる奈良漬けは白瓜などの野菜を塩漬けした後、酒粕を替えながら繰り返し漬け込んだものです。
発酵、熟成によりデンプンが糖に変化して甘味が増し風味がかもし出されます。
粕床を替えながら繰り返し漬けることで、美しいべっこう色と芳醇な香り、深みのある甘辛味の奈良漬けになります。
奈良時代の木簡(もっかん)に「加須津毛瓜」の記述があります。
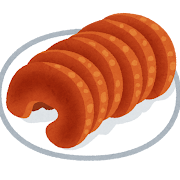
わさび漬け
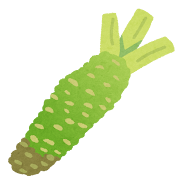
わさび漬けは静岡県の名産品です。
わさびの根と茎を刻んで塩漬けした後、酒粕に漬け込んだ物です。
江戸時代宝暦年間(1751〜1764)に現在の静岡市内で販売され、明治時代に全国に知られるようになったといわれています。
わさび特有のさわやかな刺激が酒粕のコクやうま味と調和して独特な風味になっています。
その他の漬物
すんき漬け
すんき漬けは、長野県木曽地方の伝統的な漬物で、カブの葉(すんき菜)を使った乳酸発酵食品です。特徴的なのは、塩を使わず、湯通ししたカブの葉を自然発酵させて作る点です。塩分が含まれないため、健康志向の食品としても注目されています。
すんき漬けは、酸味のあるさっぱりとした味わいで、地域ではそばと一緒に食べる「すんきそば」も人気です。また、発酵食品としての乳酸菌効果が腸内環境を整えるとも言われています。
からし漬け
からし漬けは、野菜をからし(芥子)と塩、砂糖、酢などで漬け込んだ漬物です。使用される野菜は、主に大根、ナス、キュウリなどが一般的です。からしのピリッとした辛味と、調味料の甘さや酸味が合わさった、風味豊かな味わいが特徴です。
からし漬けは、ご飯のお供として親しまれており、特に大根のからし漬けはシャキシャキとした食感と辛味が絶妙で、漬物の中でも人気があります。
おこもじ
長野県の一部地域で作られる伝統的な漬物で、特に野沢菜の浅漬けを指すことが多いです。「おこもじ」とは、地方の方言で「お漬物」や「小漬け」の意味を持ち、野沢菜などの葉物野菜を軽く塩で漬けたものです。
おこもじは、塩加減が控えめで、浅漬けならではのシャキシャキとした食感と、野菜本来の風味を楽しむことができます。食卓でのご飯のお供やお茶漬けにすることが多く、家庭の味として親しまれています。
品漬け(しなずけ)
長野県の伝統的な漬物で、特に木曽地方で親しまれている漬物です。主に白菜や大根などの野菜を、ぬかや塩で漬け込み、発酵させて作ります。古くからの保存食として、寒冷な地域で冬に備えて作られてきました。
品漬けは、ぬか漬けのような乳酸発酵が進んだ漬物で、酸味があり、発酵の風味とシャキシャキした食感が特徴です。野菜の旨味とともに、発酵食品としての健康効果も期待されています。

いかがでしたか?
日本全国でその土地の食材を生かし漬物はたくさんあります。ご紹介したものはほんの一例です。
おでかけ先などで「漬物」を覗いてみてくだい。昔の人の知恵も学べますよ。
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社
WordPress 初心者 ウイスキー 発酵酒 スピリッツ ジン ラム テキーラ 発酵酒 チーズ 発酵乳製品 パン 発酵食品 リキュール 香味酒 ワイン 発酵酒 便秘 酸化 免疫 アレルギー 冬の発酵食品、風邪予防、あったかメニュー、塩麹、味噌スープ 冷え性 善玉菌 悪玉菌 日和見菌 塩辛 魚 発酵食品 心 やさしい時間 心 乱れ 葛藤 心 健康 心 免疫 温活 発酵の里こうざき、発酵スポット、千葉、道の駅、発酵食品 発酵珍味 くさや このわた うるか めふん 日本の食文化 発酵食品 発酵調味料 塩麹 醤油麹 味噌 発酵食品 初心者向け 発酵調味料 辛味調味料 旨味 かんずり 豆板醤 コチュジャン 発酵調味料 酢 米酢 黒酢 本みりん 料理初心者 発酵調味料 醤油 魚醤 発酵食品 初心者向け 発酵食品 発酵食品 発酵産業 発酵食品 腸活 コンビニ腸活 発酵生活 健康習慣 発酵食品 腸活 免疫力 健康習慣 発酵食品 腸活 心の健康 健康習慣 発酵食品 腸活 美肌 発酵食品 腸活 腸内環境 免疫力 健康習慣 無理しない健康 発酵食品 麹 発酵食品 麹菌 酵母菌 乳酸菌 腸活 腸内環境 発酵食品、免疫力アップ、腸活、冬の健康、味噌、納豆、ヨーグルト 腸 自律神経 腸の冷え 風邪予防 腸活 冬の体調管理 腸内フローラ 発酵食品 腸内細菌 免疫力 腸内細菌 病気 腸内細菌 肥満 腸内細菌 脳 腸活 酢漬け 酢 発酵食品 免疫力 疲労回復 美容 魚 削り節 発酵食品 魚の発酵食品 鰹節 へしこ ふなずし なれずし アンチョビ


