こんにちは、garesuです。
これまで発酵食品についてお話してきましたが、
ここからは「腸の中で働く小さな仲間たち」——腸内細菌と発酵食品の関係について、
そして、発酵食品がどのように私たちの健康や免疫力を支えてくれるのかを
やさしくお伝えしていきますね。
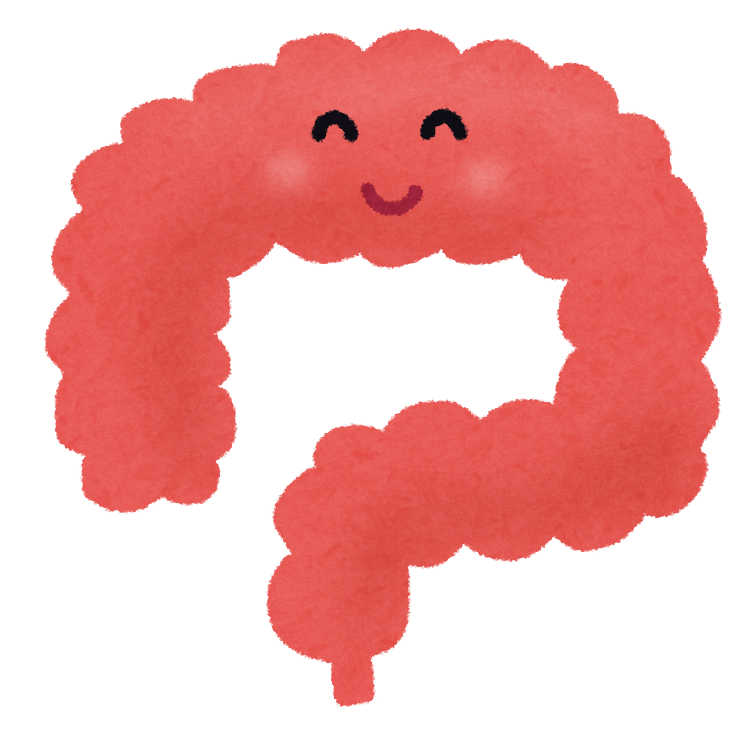
腸が元気なら、体も心も元気
最近よく耳にする「腸活」。
テレビや雑誌でも、“腸を整えると健康になる”と紹介されることが増えました。
実は、私たちの腸の中には 100兆個以上の微生物 が暮らしていて、
そのバランスが体調にも心にも深く関わっています。
腸内の環境をいい状態に保つためには、
毎日の食事で発酵食品を少しずつ取り入れることがとても大切なんです。
腸内フローラ
食べ物の通り道:消化器官の流れ
消化管は口から肛門までが一本の管(かん)になっています。
1 口(くち)
歯で噛み砕き、唾液(だえき)で消化酵素がデンプンの分解を開始します。
食塊(しょっかい)と呼ばれる状態にして次の段階へ。
2 咽頭(いんとう) → 食道(しょくどう)
飲み込むことで、食道を通って胃へ送られます。
「蠕動運動(ぜんどううんどう)」という筋肉の動きで運ばれます。
3 胃(い)
胃液(胃酸と酵素)でタンパク質を主に分解
数時間かけてドロドロの状態(胃内容物)になります。
4 小腸(しょうちょう)
十二指腸 → 空腸 → 回腸 の順で通過
胆のうやすい臓からの消化液も加わり、栄養素の大部分が吸収される
5 大腸(だいちょう)
残った水分やミネラルを吸収
腸内フローラの働きで一部の栄養が発酵・分解されます。
最終的に便として形成
6 直腸 → 肛門(こうもん)
排便反射によって、不要なものが体外へ排出されます。
※ 口 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 直腸 → 肛門
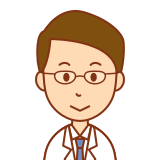
小腸の構成
成人の小腸の全長は6メートルほどあります。口に近い方から十二指腸、空腸、回腸という3つの部位で構成されています。内側の表面は絨毛(じゅうもう)とよばれる突起で覆われ、その表面積はテニスコート1面分相当になります。
腸内フローラとは?
腸の中をのぞいてみると、
まるで“花畑(フローラ)”のように、さまざまな菌たちが共に暮らしています。
これが「腸内フローラ」と呼ばれるもの。
腸内細菌たちは、
- 食べたものを分解して栄養を吸収しやすくする
- 免疫力を高めて病気を防ぐ
- ビタミンをつくる
- 心のバランス(メンタル)を整える
など、実に多くの役割を果たしています。
腸内環境が整うと、美肌・便通改善・ダイエット効果なども期待できます。
まさに「健康もキレイも、腸からはじまる」んですね。
主な働き
消化の補助
食べ物を分解し、栄養素の吸収を助けます。
免疫力の維持
悪玉菌の増殖を抑え、病気にかかりにくくします。
ビタミン合成
ビタミンB群やビタミンKなどを腸内で生成します。
メンタルへの影響
最近の研究では、「腸脳相関」と呼ばれる仕組みにより、ストレスや気分にも影響を与えることが分かってきました。
腸内フローラを整えるには?
発酵食品を摂取(ヨーグルト、納豆、キムチ など)
食物繊維を意識(野菜、果物、海藻類)
規則正しい生活と適度な運動
必要に応じてプロバイオティクスやプレバイオティクスのサプリを活用
腸内環境を整えることで、美肌・便通改善・ダイエット効果なども期待できます。
腸内細菌の種類
腸内には、数百〜数千種類もの細菌が存在し、健康に大きな影響を与えています。
主に以下の3つのタイプに分類されます。
善玉菌とは? 〜腸の”味方チーム”〜
善玉菌(ぜんだまきん)は、腸内で健康によい働きをする細菌です。
悪玉菌の増殖を抑えたり、免疫をサポートしたりと、私たちの体の中で多くの役割を果たしています。
| 善玉菌の種類 | 特徴・働き |
|---|
| ビフィズス菌 | 大腸に多く存在。乳酸と酢酸を作り、悪玉菌を抑制 |
| 乳酸菌(ラクトバチルス) | 小腸に多く、乳酸を生成して腸内を酸性に保つ |
| 酪酸菌(クロストリジウム属など) | 酪酸を作り、腸のバリア機能を高める |
| エンテロコッカス属 | 免疫細胞を活性化し、感染症予防に役立つこともあります |
これらの菌たちは、発酵という働きで
酢酸や乳酸、酪酸などの「短鎖脂肪酸」を作り出します。
短鎖脂肪酸は、腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を防ぐと同時に、
腸のぜん動運動を促して、便通をよくしてくれます。
腸が動けば、気分も軽くなる。
そんな経験、ありませんか?
腸内のバランスが整うと、免疫力も自然と高まり、
風邪をひきにくくなったり、肌の調子がよくなったり。
まさに、「善玉菌は体の中のやさしい守り神」なんです。
善玉菌の働き
腸内の悪玉菌を抑える
酸を出して悪玉菌の住みにくい環境を作る。
免疫機能の強化
体内の免疫細胞を刺激し、風邪やアレルギーを予防。
栄養の合成と吸収
ビタミンB群やKなどの合成を助ける。
整腸作用
便通を良くし、便秘や下痢の予防に貢献。
美肌・メンタルケア
腸内環境が整うと、肌荒れが改善され、ストレスにも強くなることが知られています。

善玉菌は短鎖脂肪酸を生成することで腸内を弱酸化の状態に保ち、悪玉菌の侵入や増殖を防いでくれます。
また、短鎖脂肪酸には大腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、排便を促すことで腸内の有害物質を体の外へ排出する働きもあります。
善玉菌を増やすには?
善玉菌は、毎日の食事で少しずつ育てていくことができます。
おすすめの食べ物
- 発酵食品(ヨーグルト・納豆・味噌・キムチ・ぬか漬けなど)
- 食物繊維(野菜・果物・海藻類)
- オリゴ糖(玉ねぎ・バナナ・大豆製品)
生活の中で意識したいこと

- ストレスを溜めない
- 睡眠をしっかりとる
- 適度な運動を続ける
「発酵食品を食べることは、腸の中の“仲良しチーム”を応援すること。」
今日から、そんな気持ちで1日1回の発酵習慣を続けてみませんか?
悪玉菌とは? 〜腸の中の”ちょっと困ったさん”〜
腸内に住む細菌たちは、私たちの健康を支える大切な存在。
でも、なかには「悪玉菌」と呼ばれる、少しやっかいなタイプもいます。
悪玉菌は、動物性のたんぱく質や脂質を分解するときに、
アンモニアや硫化水素などの腐敗ガスを発生させます。
これが便やおならのニオイの原因になることもあるんです。
悪玉菌は少量なら腸のバランスに必要ですが、
増えすぎると便秘や肌荒れ、体臭、免疫低下など
さまざまな不調を引き起こす原因にもなります。
| 悪玉菌の種類 | 特徴・作用 |
|---|---|
| ウェルシュ菌 | 肉類中心の食生活で増加。腐敗物質を作り、便臭・体臭の原因に。 |
| 有害な大腸菌(毒素産生株) | 食中毒の原因になることも。腸内の炎症を引き起こす。 |
| ブドウ球菌 | 感染症や炎症を引き起こす場合がある。免疫が落ちると増殖。 |
| クロストリジウム属(悪性株) | 毒素を出し、腸内の炎症や下痢を引き起こす。 |
悪玉菌が増えると、腸の中が「腐敗モード」に傾き、
腸壁のバリアが弱まってしまいます。
すると、有害物質が血液に入り込み、全身に回ってしまうことも‥
「最近、疲れやすい」「肌がくすむ」と感じるときは、
もしかしたら腸の中で悪玉菌が元気になりすぎているサインかもしれません。
悪玉菌が増えるとどうなる
腸内の腐敗ガス(アンモニア・硫化水素など)が増加
便秘・下痢などの腸の不調
肌荒れ・口臭・体臭が目立つ
免疫力の低下
老化促進や生活習慣病リスクの増大(動脈硬化・大腸がんなど)
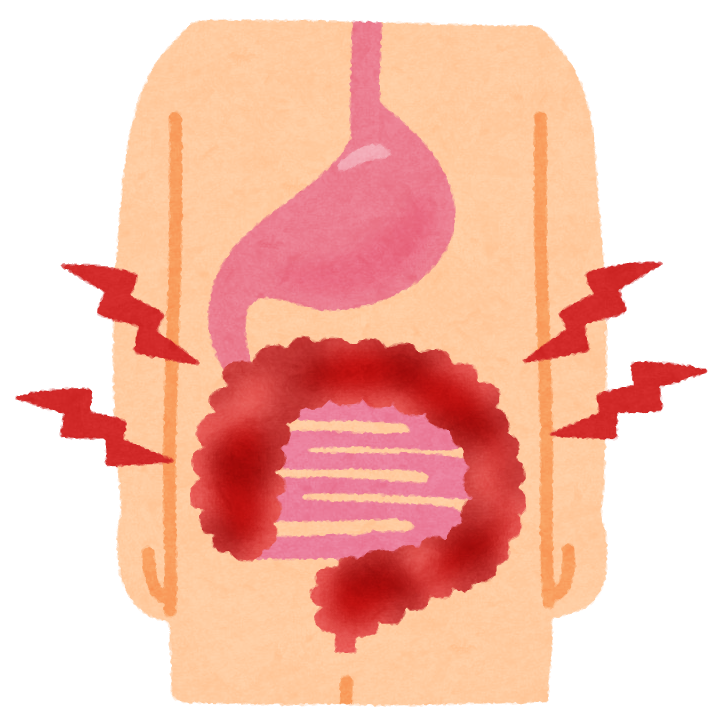
腸内の悪玉菌が増えると蠕動運動の力が弱まり、便秘や下痢など排便が乱れがちになります。
便秘は肌荒れの原因になるほか、有害物質が腸の中に長くとどまることで、ますます悪玉菌の数が増えてしまいます。
また、善玉菌が優勢のときは、腸壁の粘膜がバリアとなって有害物質が体内に入り込まないように守ってくれますが、悪玉菌が優勢な状態が続けば粘膜のバリア機能が弱まり、有害物質が腸壁を通って血液に吸収されやすくなってしまいます。
血液にのって全身にひろがった有害物質は内臓の不調を引き起こし、がんや生活習慣病の原因となります。
悪玉菌が増える原因
肉類・脂肪中心の食生活
野菜・発酵食品の不足
過度なストレス
睡眠不足
抗生物質の乱用(善玉菌も殺してしまう)
悪玉菌を減らす3つのポイント
1 発酵食品を意識して摂る
→ 納豆・味噌・ヨーグルトなど、腸が喜ぶ発酵食品を毎日少しずつ。
2 食物繊維とオリゴ糖をプラス
→ 野菜・果物・海藻・玉ねぎ・大豆などは善玉菌のエサになります。
3 ストレスを減らして、しっかり眠る
→ ストレスホルモンは腸の動きを弱めるので、深呼吸も大切。
腸の中のバランスを保つには、
「悪玉菌を減らす」よりも「善玉菌を育てる」意識がポイントです
日和見菌(ひよりみきん)とは? 〜空気を読む”調整薬”〜
腸内にいる菌の中で、一番多いのが日和見菌(ひよりみきん)。
全体の約70%を占めていて、
腸の“空気”を読みながら、善玉にも悪玉にもなる不思議な存在です。
善玉菌が優勢なときは、善玉菌の味方。
でも、悪玉菌が増えてくると、悪玉の仲間になってしまうことも💦
つまり、腸内で善玉菌をしっかり育てることが、日和見菌を味方につける秘訣なんです。
日和見菌は、腸内細菌のバランスにおいてとても重要なポジションを占める存在であり、健康維持にも深く関わっています。
日和見菌の主な種類と特徴
| バクテロイデス属 | 通常は無害。腸内でタンパク質や糖の代謝を助けるが、バランスが崩れると炎症の原因になることも。 |
| 連鎖球菌(ストレプトコッカス属) | 一部は善玉菌の役割を果たすが、口腔や腸内で炎症を引き起こすことも。 |
| 大腸菌(無毒株) | 正常な腸内にも存在するが、バランス悪化で有害株と競合する場合がある。 |
日和見菌は、「腸の空気を読む名人」。
善玉菌が元気だと、その波にのって腸を整える方向に動いてくれます。
日和見菌を味方につける生活習慣
- 発酵食品と野菜を毎日少しずつ
- 睡眠・リラックス時間を大切に
- 腸に優しいお茶(白湯・ルイボスティーなど)で冷えを防ぐ
腸の中に“やさしい空気”を作ることが、
日和見菌の良い動きを引き出すコツなんです。
理想的な腸内バランス
| 菌のタイプ | 割合 |
|---|---|
| 善玉菌 | 約20% |
| 悪玉菌 | 約10% |
| 日和見菌 | 約70% |
この黄金バランスを保つことが、
健康にも美容にも欠かせない“腸内ハーモニー”
腸が穏やかだと、心も穏やかになります。
だからこそ、「今日の食事で腸を笑顔にする」ことを意識してみてください。

いかがでしたか?
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、
私たちの体と心の健康を左右しています。
発酵食品を味方にすれば、腸はしっかり働き、
免疫力も上がり、毎日を軽やかに過ごせます✨
🌿 「腸がよろこぶ食卓は、心も整える」
そんな想いで、今日から小さな発酵習慣をはじめてみませんか?
お味噌汁を1杯、納豆を1パックからで十分です。
腸を整えることは、自分をいたわること。
発酵の力で、内側からの元気を育てていきましょう
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


