こんにちは、garesuです。
チーズは大好き!という方は多くいらしゃると思います。
チーズについてお伝えしますね。
乳を発酵させて作られる発酵乳製品の一つです。
乳を凝固させ、その凝固物を固めたり熟成させたりして作ります。
乳を凝固させるためには、乳酸菌やレンネットといった酵素が使われます。チーズは牛乳、羊乳、ヤギ乳、バッファロー乳など、さまざまな動物の乳から作られることがあります。
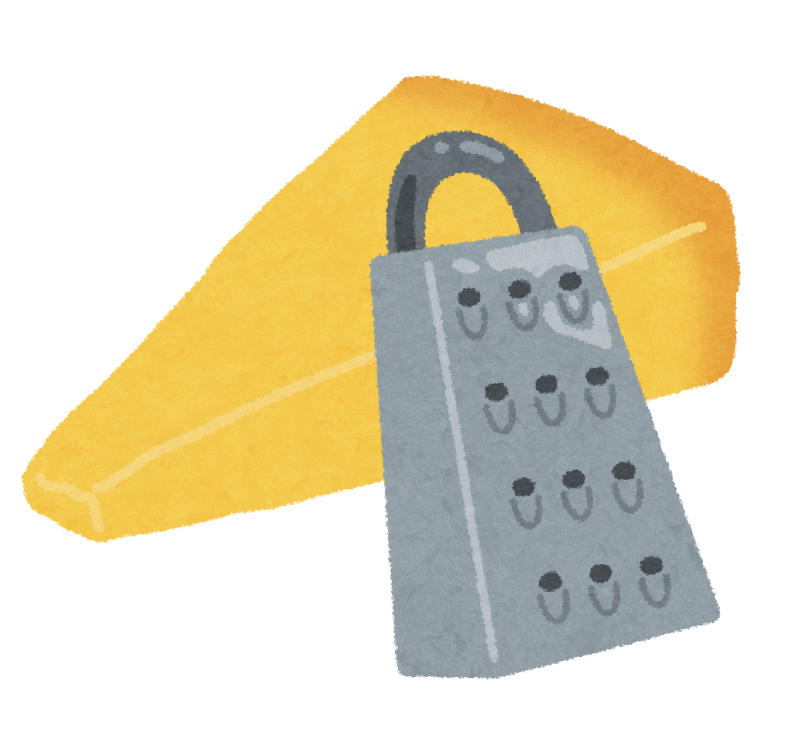
世界には1000種類以上のチーズがあるといわれ、それらはナチュラルチーズとプロセスチーズの2種類に大きく分けられます。
チーズの歴史
チーズの歴史はとても古く、約7000年以上前にさかのぼるとされています。
古代の起源
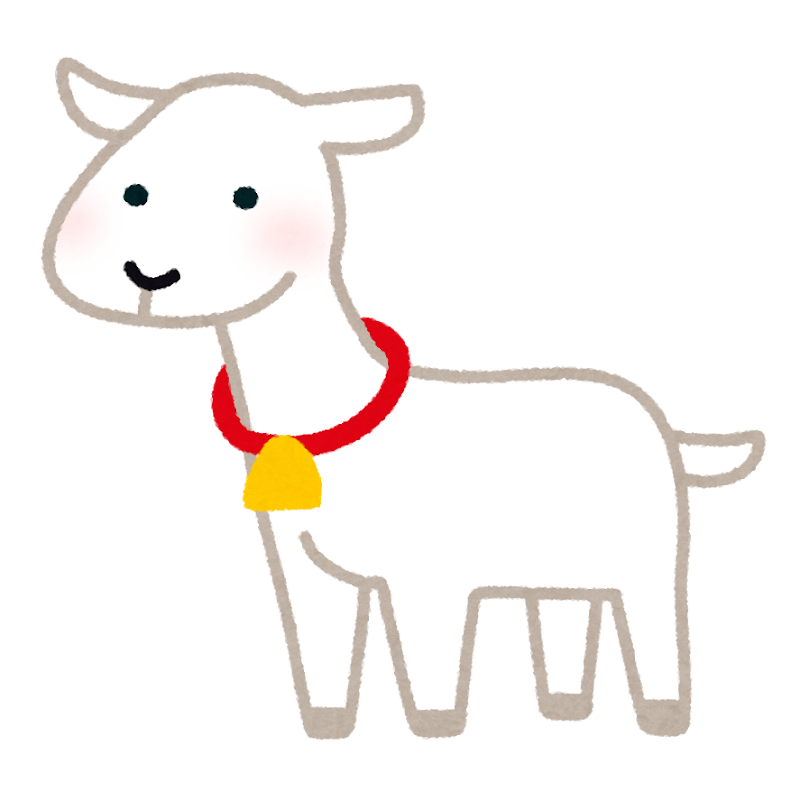
チーズの発明がどのようにして起こったのか、正確な記録はありませんが多くの歴史家は、乳を長期間保存するための偶然の発見がきっかけだと考えています。
初期のチーズ製造は、遊牧民が動物の胃袋を使って乳を運搬した際、胃袋に含まれていた酵素(レンネット)が乳を凝固させ、チーズができたという説が有力です。
紀元前5000年頃: 中東や中央アジアの遊牧民が、乳を長期保存するためにチーズのような乳製品を作っていたとされています。
実際、古代メソポタミアの壁画には、乳を処理している様子が描かれており、この地域でチーズが生産されていたことが示唆されています。
紀元前2000年頃: 古代エジプトでは、墓の中にチーズが埋葬された記録があり、ここからもチーズが当時の重要な食品であったことがわかります。
古代ギリシャ・ローマ時代
古代ギリシャとローマでは、チーズは日常の食生活の中で広く使われていました。
特に古代ギリシャでは、ホメロスの『オデュッセイア』にもチーズ作りの描写があり、羊乳やヤギ乳からチーズが作られていたことがわかります。
古代ギリシャ: チーズは神々への捧げ物としても使われ、健康食品としても重宝されていました。
フェタチーズのような現在でも人気のチーズの原型は、この時代に発展したと考えられます。
古代ローマ: ローマ帝国の拡大に伴い、チーズ製造技術はヨーロッパ全土に広がりました。
ローマ人はさまざまな種類のチーズを作り、保存のために塩を使うなどの技術を発展させました。
また、ローマ軍の兵士たちは、遠征中の食料としてチーズを持ち歩きました。
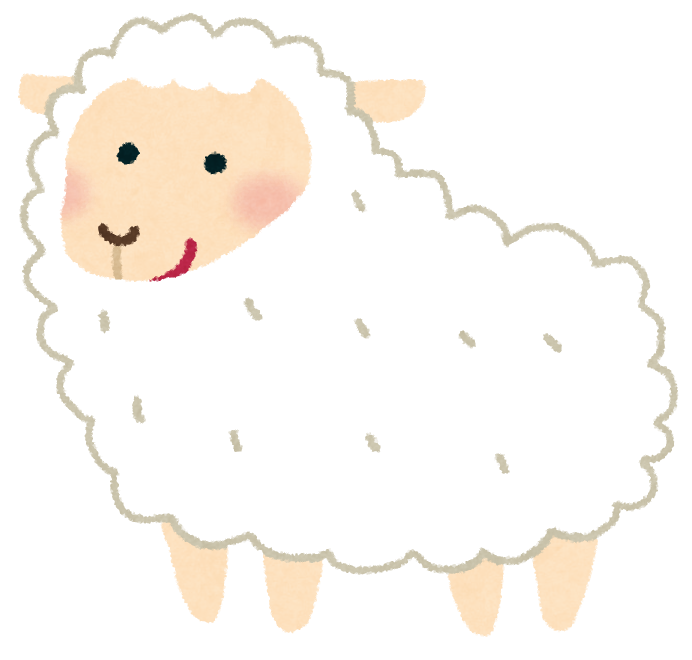
中世ヨーロッパ
中世に入ると、チーズの製造は主に修道院で行われるようになりました。
修道士たちは、特にヨーロッパのアルプス地方などでチーズの品質を向上させ、熟成の技術も洗練されました。
この時期に発展した多くのチーズは、今日でも有名なものが多く、たとえばカマンベールやパルミジャーノ・レッジャーノ、ロックフォールなどがあります。
フランス: この時代にフランスでは、多くの地方ごとに特徴のあるチーズが作られ、チーズ文化が発展しました。
修道院や農家がチーズを製造し、地域ごとの風味や製法が確立されました。
イタリア: イタリアでも、パルミジャーノ・レッジャーノやモッツァレラなど、さまざまな種類のチーズが発展しました。
今日でも世界中で親しまれています。
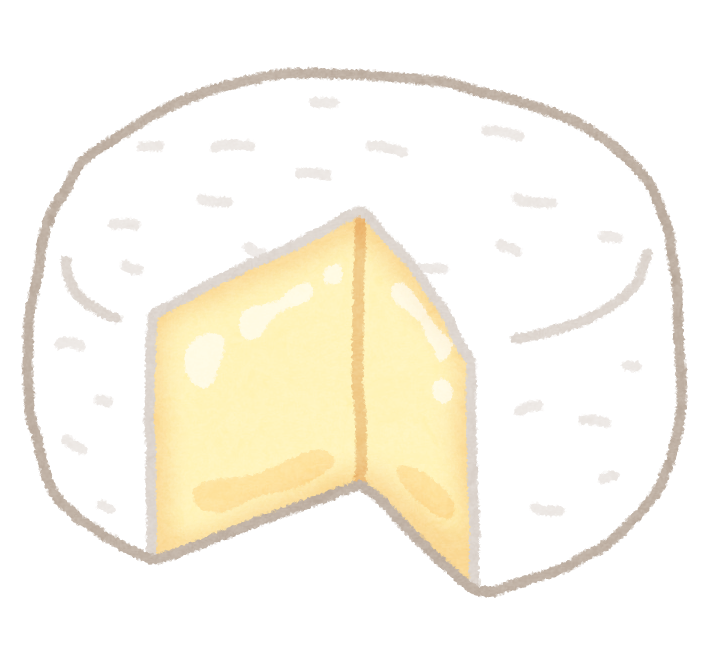
近代
近代に入ると、チーズの製造はますます規模を拡大し、産業化されました。
18世紀後半から19世紀にかけて、特にヨーロッパやアメリカでチーズ工場が建設され、大量生産が可能になりました。
また、チーズの保存技術が進歩し、長期保存や輸出も可能となりました。
19世紀: 1815年、スイスで最初のチーズ工場が設立され、その後アメリカでもチーズの工業生産が広がりました。これにより、チーズの生産量が飛躍的に増加しました。
20世紀: 20世紀に入ると、冷蔵技術や包装技術が進歩し、チーズはより幅広い地域に供給されるようになりました。また、ピザやハンバーガーの普及により、モッツァレラやチェダーなどのチーズが世界的に人気を集めました。
現代
現在では、世界中で数千種類ものチーズが作られています。
伝統的な手法で作られる職人技のチーズから、大規模に生産される工業製品まで、さまざまな種類があります。
また、地域や国ごとにチーズに関する法律や保護制度が設けられており、特定の地域で作られるチーズには「原産地呼称保護(AOP)」などの認定が与えられることもあります。
日本のチーズの始まり
日本におけるチーズの歴史は、比較的最近のものであり、欧米に比べるとその普及は遅れています。
しかし、日本には古くから「乳製品」を食べる文化が存在しており、チーズの導入も次第に進んでいきました。
奈良時代の「蘇(そ)」
日本における乳製品の歴史は、奈良時代(8世紀)にまでさかのぼります。
この時代に存在していたのは「蘇(そ)」と呼ばれる乳製品です。
蘇は現在のチーズに近いものではなく、牛乳を煮詰めて作った非常に硬い乳製品でした。
これは、当時の日本において、貴族や僧侶が健康や栄養のために珍重していた高級食品でした。
蘇は、唐(中国)や朝鮮半島から伝わった技術と考えられており、『延喜式』などの文献にもその製法が記されています。
蘇は長期間保存できるもので、主に儀式や貴族への献上品として使われていました。
これは現代のチーズとは異なるものの、日本における乳製品の最初の歴史的な形と言えます。
江戸時代の乳製品
その後、日本では乳製品の文化はほとんど発展せず、チーズのような製品が広がることはありませんでした。
牛乳自体があまり普及しておらず、江戸時代(17〜19世紀)には、乳製品は一般的なものではありませんでした。しかし、オランダからの西洋の影響により、長崎の出島では一部の日本人がチーズを試した記録が残っています。
明治時代の西洋化とチーズの導入
本格的にチーズが日本に入ってきたのは、明治時代(1868年〜1912年)です。この時期、日本は西洋の技術や文化を積極的に受け入れる「文明開化」の時代を迎えました。
西洋文化が導入される中で、牛乳やバター、チーズなどの乳製品も日本に紹介されるようになりました。
特に、1875年には「北海道開拓」に伴い、外国からの技術者や農業指導者が日本にチーズ製造の技術をもたらしました。
北海道は、牛の飼育に適した環境であり、乳牛の飼育が奨励されました。北海道では乳業が発展し、これが日本におけるチーズ生産の基盤となります。
大正時代から昭和時代のチーズの普及
大正時代(1912年〜1926年)から昭和時代(1926年〜1989年)にかけて、乳製品産業が徐々に発展していきました。特に、北海道での乳業の発展により、バターやチーズの生産が本格化しました。しかし、一般家庭でチーズが日常的に食べられるようになるのは、まだ先のことでした。
第二次世界大戦後、アメリカの影響を受け、日本でも洋食文化が広まり、チーズの消費量が徐々に増えていきました。
ピザやグラタンなど、西洋料理が家庭に浸透するにつれて、チーズは一般家庭にも普及していきました。
特にプロセスチーズが手軽で保存が効くことから、広く消費されるようになりました。
1980年代以降のチーズブーム
1980年代以降、日本では食の多様化が進み、海外からのチーズが輸入されるようになりました。
特に、ナチュラルチーズへの関心が高まり、スーパーマーケットでも輸入チーズが手軽に購入できるようになりました。
これに伴い、日本国内でもチーズの消費が急増し、ワインと合わせて楽しむスタイルや、チーズ料理の専門店も増えていきました。
また、北海道や長野県などを中心に、国内でもナチュラルチーズの生産が盛んになり、品質の高い国産チーズが評価されるようになりました。日本の気候や風土に適したチーズが作られ、近年では国際的なチーズコンテストで賞を受賞する日本産チーズも出てきています。
現代の日本のチーズ文化
現在、日本のチーズ市場は大きく成長しています。チーズは日常的な食材として定着し、料理の材料としても多く使われるようになっています。
また、ナチュラルチーズの愛好家も増えており、熟成チーズやブルーチーズなど、さまざまな種類のチーズが楽しまれています。
チーズフェスティバルやワークショップなど、チーズに関するイベントも各地で開催され、チーズ文化はますます広がりを見せています。
いかがでしたか?
そのまま食べたり、お料理に使ったりと幅広い用途で親しまれているチーズ、これからも変わらず愛され続けられることでしょう。

参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


