こんにちは、garesuです。
風味豊かでご飯にも合い、野菜不足の解消にも役立つ漬物。
日本の伝統的な保存食で、野菜や果物を塩や酢、味噌、酒粕などに漬け込んで発酵させた食品です。日本では古くから食卓に欠かせない存在であり、季節ごとの食材を使ったり、地域によってさまざまな種類の漬物が楽しめます。
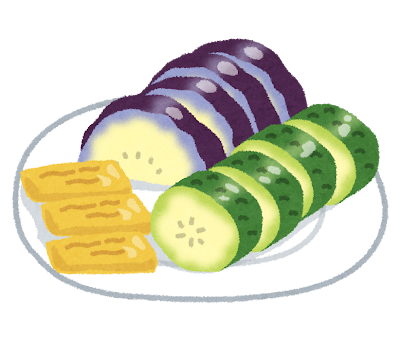
漬物の歴史
塩漬けから始まった漬物
漬物について詳しく書かれている文献は、6世紀中頃の中国の農業技術書斉民要術(せいみんようじゅつ)です。
そこには、野菜に穀物を加えて塩漬けにする方法と記されています。
日本では奈良時代の文献や平城京跡から見つかった木簡(もっかん)に青菜やカブ、瓜などを大豆や米などの穀物と塩で漬けた「須々保利」(すずほり)やニレ科植物の樹皮の粉末と塩で食材を漬けた「楡木」(にらぎ)などの漬物の名前が登場します。
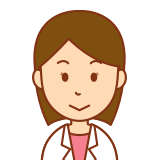
木簡とは‥細長い木の板に文字をきしたもの。
役所の記録や荷札などに用いられた。
平安時代の法令集「延喜式」(えんぎしき)には、漬物として塩漬けや醤漬け(ひしおづけ)など現在の漬物にも通じる色々な漬物の製法が記載されています。
平安時代(794年~1185年)
貴族たちの食事にも漬物が登場し始めます。この時期は主に塩漬けが中心でしたが、味噌漬けや酒粕漬けも登場しました。特に宮廷料理において、塩や味噌を使った保存食品としての漬物が重宝されました。また、この頃から漬物が食事の一部として定着し始めたとされています。
鎌倉~室町時代(1185年~1573年)
鎌倉時代には武士の生活が台頭し、漬物はより一般的な食品として広まります。戦国時代の武士たちは、保存性の高い漬物を携帯食として重宝しました。この時代には、食材を塩だけでなく、醤油や酢、味噌などで漬ける方法がさらに発展しました。
また、室町時代には禅僧たちの影響で「精進料理」が普及し、その中で野菜の漬物が重要な役割を果たしました。健康を保つために、漬物が日常的に消費されるようになったのです。
江戸時代(1603年~1868年)
江戸時代になると、庶民の間でも漬物が大変人気となります。この時代は発酵技術がさらに発達し、乳酸菌を利用した「ぬか漬け」が普及しました。この頃から「香の物」という言葉が使われるなり京都や大阪では香の物屋という漬物専門店も登場しました。
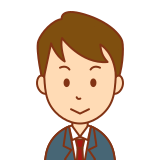
香の物とは‥
漬物のことを「香の物」と呼ぶようになったのは、お香の香りを鑑賞する聞香(もんこう)の際嗅覚を正すために大根の漬物を噛んだことに由来する。
ぬか漬けは、米ぬかを使って簡単に漬けられ、家庭で手軽に作れるため、庶民の間で非常に広まりました。また、江戸時代には漬物専門の商人も現れ、さまざまな種類の漬物が都市部で売られるようになります。
明治時代以降(1868年~)
明治時代に入り、日本の食文化は西洋の影響を受けながらも、漬物は依然として家庭料理の一部として根強く残りました。冷蔵技術の発展によって保存方法が多様化しましたが、漬物は保存食としてだけでなく、風味を楽しむための食品としても定着しました。
さらに、全国各地で地域特有の漬物が発展し、地方の特産品としても広く認識されるようになりました。例えば、京都の「千枚漬け」、長野の「野沢菜漬け」、秋田の「いぶりがっこ」など、各地で独自の発展を遂げた漬物が存在します。
現代の漬物
現代においても、漬物は健康食品として再評価されています。特に乳酸菌や食物繊維が豊富なことから、腸内環境を整える効果が注目されています。また、簡便化や食材の多様化により、スーパーで手軽に購入できる漬物も多くなりつつありますが、家庭で自作する人も少なくありません。漬物は、単なる保存食から健康食、さらには伝統文化として、現代でも多くの人々に愛されています。
漬物の種類
漬物は、発酵させるかどうかによって大きく「発酵漬物」と「無発酵漬物」に分類されます。
1. 発酵漬物
発酵漬物は、微生物(主に乳酸菌)の働きによって食材が発酵し、特有の風味と栄養価が高まる漬物です。発酵過程では乳酸菌が野菜の糖分を分解して乳酸を生成し、酸味や旨味が加わります。発酵による乳酸菌の生成は腸内環境を整える効果があり、健康にも良いとされています。
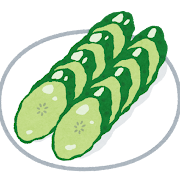
特徴
乳酸菌による発酵で酸味や独特の風味が生まれる。
発酵によってビタミンやアミノ酸などの栄養価が向上する。
保存性が高く、長期保存が可能な場合が多い。腸内環境を整える効果が期待できる。
代表的な発酵漬物
ぬか漬け:米ぬかに野菜を漬け込み、乳酸菌の発酵を利用して作る漬物。発酵が進むことで、酸味が強くなることがあります。きゅうり、ナス、大根などがよく使われます。
たくあん:干した大根をぬかや塩と一緒に漬け込み、乳酸発酵させた漬物。日本を代表する発酵漬物のひとつです。
キムチ:白菜や大根などを唐辛子、ニンニク、塩、魚醤などと共に漬け込み、乳酸菌で発酵させた韓国発祥の漬物。発酵が進むにつれて酸味が増します。
高菜漬け:高菜を塩と共に漬け込み、発酵させて作る九州地方の伝統的な漬物。炒め物やおにぎりの具材としても人気です。
しば漬け:ナスやキュウリなどを赤紫蘇とともに漬け込み、発酵させた京都の漬物。
2. 無発酵漬物
無発酵漬物は、発酵させずに調味料で味をつける漬物です。発酵を行わないため、漬け込む時間が短くて済み、比較的短期間で食べることができるのが特徴です。無発酵漬物は、食材本来の味や食感をより強く感じることができます。
特徴
発酵を行わないため、酸味が少なく、素材の味が活かされる。
短時間で漬け込むことができるため、作るのに手間がかからない。
風味をつけるために、塩、酢、醤油、砂糖などの調味料を用いる。保存性は発酵漬物に比べると低い。
代表的な無発酵漬物
浅漬け:塩や調味液に野菜を短時間漬けて作る即席漬物。発酵は行わず、素材の風味と調味料のバランスを楽しむことができます。きゅうりや大根が一般的です。
ガリ(甘酢生姜):酢と砂糖で生姜を漬けたもので、発酵はしません。寿司に添えられる定番の漬物です。
らっきょう漬け:らっきょうを甘酢に漬けたもので、酸味と甘みが調和した味わいです。
奈良漬け:瓜や大根を酒粕で漬けたもので、発酵ではなく酒粕の風味が強く現れる漬物。保存期間は長めです。
梅干し(しそ漬けなど、短時間漬けるもの):一部の梅干しは発酵を行わない方法で作られ、梅を短時間で塩や紫蘇に漬けて風味をつけたものもあります。
まとめ
- 発酵漬物:乳酸菌の発酵による酸味や旨味が特徴で、腸内環境を整える効果が期待できる。ぬか漬け、たくあん、キムチなどが代表例。
- 無発酵漬物:調味料によって素材の風味を引き出し、短時間で漬け込む。浅漬け、甘酢漬け、奈良漬けなどが代表例。
どの漬物も、日本の食文化に欠かせない存在であり、食事に彩りや健康効果をもたらします。
日本各地の代表的な漬物です。
| 地域 | 漬物の名称 | 主な材料 | 漬け方 | 発酵の有無 | 特徴・説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 松前漬け | 昆布、スルメ、野菜 | 醤油、みりんなどで漬ける | 無発酵 | スルメや昆布を使い、うま味が濃厚な漬物。シャキシャキした食感が特徴。 |
| 秋田県 | いぶりがっこ | 大根 | 燻製後、ぬかや塩で漬ける | 発酵 | 大根を燻製してからぬかで漬け込む。香ばしい香りとシャキシャキした食感が特徴。 |
| 福島県 | 味噌漬け | 野菜(大根、きゅうり) | 味噌で漬ける | 無発酵 | 味噌の旨味が野菜にしっかり染み込んだ、濃厚で深い味わい。 |
| 長野県 | 野沢菜漬け | 野沢菜 | 塩で漬け込む | 発酵 | 長野県特産の野沢菜を塩漬けし、発酵させた漬物。シャキシャキした食感と軽い酸味が特徴。 |
| 京都府 | しば漬け | ナス、きゅうり、紫蘇 | 塩と紫蘇で漬ける | 発酵 | 野菜と赤紫蘇を一緒に漬け込み、発酵させる。独特の酸味と紫蘇の風味が楽しめる。 |
| 奈良県 | 奈良漬け | 瓜、大根、ナス | 酒粕で漬ける | 無発酵 | 酒粕で漬け込んだ漬物で、深い甘みと独特の香りが特徴。奈良の伝統的な漬物。 |
| 福岡県 | 辛子明太子 | たらこ(魚卵) | 唐辛子と調味料で漬ける | 無発酵 | 魚卵を唐辛子や調味料に漬け込み、ピリッとした辛さが特徴。ご飯のお供として人気。 |
| 宮崎県 | 高菜漬け | 高菜 | 塩で漬け込み発酵 | 発酵 | 高菜を塩で漬けて発酵させた漬物。風味が強く、炒め物やおにぎりの具材としても使用される。 |
| 石川県 | かぶら寿司 | かぶ、鰤(ぶり) | 麹で漬ける | 発酵 | かぶと鰤を麹で漬けた北陸地方特有の発酵漬物。甘みと塩味のバランスが絶妙。 |
| 静岡県 | わさび漬け | わさびの茎、葉 | 酒粕で漬ける | 無発酵 | 酒粕でわさびの茎や葉を漬けたもので、ピリッとした辛さと酒粕の風味が楽しめる。 |
| 鹿児島県 | 桜島大根の漬物 | 桜島大根 | 塩で漬ける | 無発酵 | 鹿児島特産の桜島大根を使った漬物。甘みがあり、柔らかい食感が特徴。 |
| 青森県 | せんべい漬け | 大根 | 塩で漬けた後、甘酢で味付け | 無発酵 | 青森特産の南部せんべいと一緒に漬ける大根の漬物。独特の歯ごたえが魅力。 |
日本の各地で生まれた漬物の多様性や独特の文化を感じ取っていただけると思います。
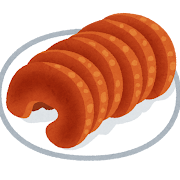
いかがでしたか?
発酵漬物の製法は次回お伝えしますね。
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


