こんにちは、garesuです。
発酵食品の「味噌」について最後の項目になります。
味噌は、風味豊かな発酵食品であり、栄養面でも健康に良い効果が期待される食品なのです。
味噌のおいしさの秘密
味噌づくりで原料を混ぜ合わせる作業を仕込みといいます。
このときに水分が少ないと発酵が進みにくく、水分が多いと発酵が進みやすくなるので種水(たねみず)で調節します。
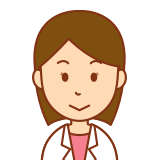
種水とは‥味噌を仕込む際に加える水のことです。
仕込みの際に酵母や乳酸菌を加えることもあります。
酵母には消臭や香り付けの効果、塩辛さを抑えて味に丸みをもたせる塩なれの効果があります。
乳酸菌にも消臭や塩なれ効果があるほかに、熟成中に酵母が繁殖しやすいようpHを整えるはたらきもあります。
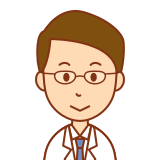
塩なれとは‥味噌の塩味 仕込み初期には塩辛く感じられた味噌は、熟成するに従って塩辛味が減少します。 この塩分濃度は同じであるのに舌に感じる塩辛味が減る現象を「塩なれ」といい、酸味や旨味成分の影響を受けた結果で、「塩なれ」させる物質として乳酸・ペプチド・アミノ酸があります。
豊かな風味と香り
・味噌は大豆を麹菌と塩で発酵させて作られるため、発酵による深い旨味(うま味)が特徴です。発酵が進むことで、アミノ酸やペプチドが生成され、複雑で奥行きのある味わいが生まれます。
・さらに、発酵中に生成される酵母や乳酸菌が、味噌独自の香りを生み出し、調理に使用すると豊かな香りが料理を引き立てます。
甘みと塩味のバランス
・米味噌や麦味噌には甘味があり、塩味とのバランスが取れています。特に白味噌は甘味が強く、味噌汁やドレッシングに使うと、まろやかな味わいになります。
・一方、豆味噌などは深いコクと強い塩味が特徴で、濃い味付けの料理に適しています。
熟成の深み
・味噌は熟成期間によって味が変わります。短期間熟成の味噌は軽やかな風味で、長期間熟成された味噌は、濃厚で深い旨味とコクを持ちます。赤味噌のような長期熟成の味噌は、色が濃く、力強い味わいを持ちます。
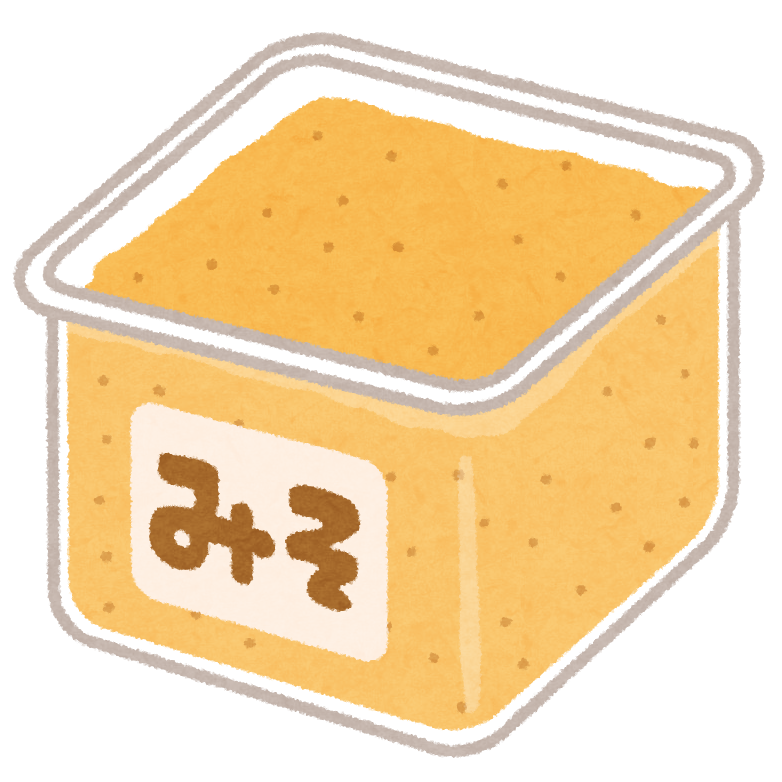
味噌の健康効果
発酵食品の健康効果
・プロバイオティクスの供給源: 味噌は発酵食品であり、乳酸菌や酵母が含まれています。これらの善玉菌は腸内環境を整え、消化機能を改善し、腸内フローラのバランスを保つ効果があります。
・免疫力の向上: 発酵によって生じる乳酸菌や酵母が、腸内の善玉菌を増やすことで、免疫力を向上させる効果が期待されています。
大豆由来の栄養素
・大豆たんぱく質: 味噌には大豆から来る良質なたんぱく質が含まれており、体内での筋肉や細胞の修復に寄与します。
・イソフラボン: 大豆にはイソフラボンという成分が含まれ、ホルモンバランスを整える作用があり、特に女性にとって健康をサポートする効果が期待されています。
・レシチン: 大豆由来のレシチンは、脳の活性化を助け、記憶力や集中力の向上にも良い影響を与えると言われています。

ビタミン・ミネラルの供給
・ビタミンB群: 味噌にはビタミンB群が含まれており、エネルギー代謝や疲労回復に役立ちます。
・ミネラル(マグネシウム、鉄、カルシウムなど): 骨や血液の健康を保つために必要なミネラルが含まれています。
抗酸化作用
・味噌には発酵によって生成された抗酸化物質が含まれており、体内の酸化ストレスを軽減し、老化や生活習慣病の予防に役立つ可能性があります。
塩分とのバランスに注意
・味噌には塩分が含まれているため、過剰摂取には注意が必要ですが、適量を摂取することで上記の健康効果を享受できます。
味噌の使い方とおいしく食べるコツ
味噌汁
・味噌の基本的な使い方であり、毎日の食卓に手軽に取り入れることができます。具材を工夫することで、栄養バランスも向上します。
・国立がんセンター研究所の故・平山雄(ひらやま たけし)博士の報告では、毎日味噌汁を飲む人は、飲まない人と比べて胃がんによる死亡率が低くなるという傾向が見られました。
これは味噌に含まれるリノレン酸エチルエステルのはたらきが関係していると考えられています。
調味料としての活用
・味噌は和風ドレッシング、煮物、焼き物、炒め物など様々な料理に使えます。甘みや旨味を活かして、肉や魚の風味を引き立てます。
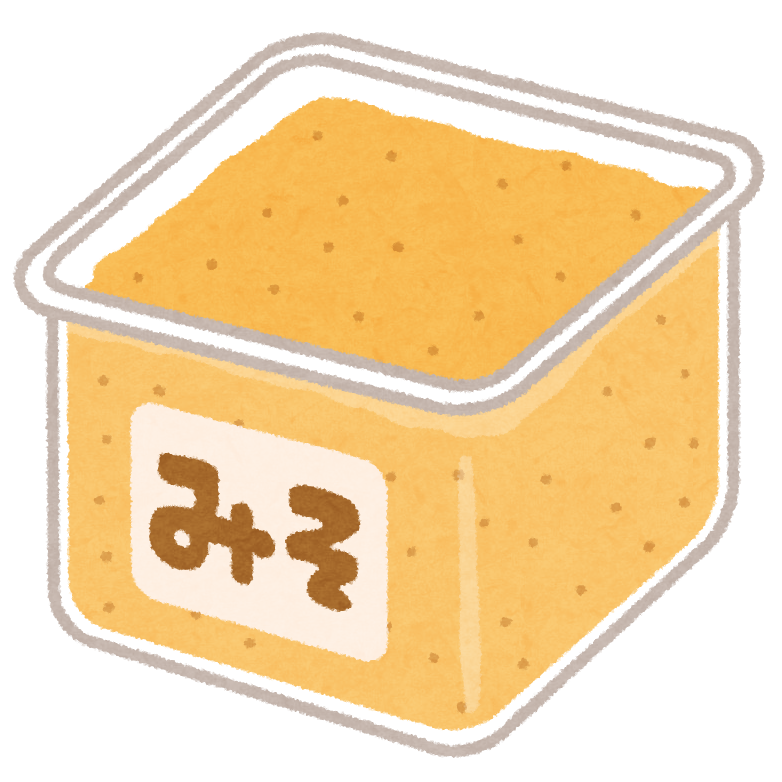
いかがでしたか?
味噌は、深い旨味と香りで料理を引き立てる発酵食品であり、腸内環境の改善や免疫力の向上など、多くの健康効果も期待されます。毎日の食生活に取り入れることで、味の楽しみと健康を両立できる素晴らしい食材なのです。
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


