こんにちは、garesuです。
みりんの「原料」からお伝えしますね。
みりんの原料
みりんの主な原料は3つです。
もち米: みりんに使用されるお米は「もち米」です。もち米は、通常の米よりも粘り気が強く、甘みを引き出すために重要な役割を果たします。
米麹(こめこうじ): 米を発酵させた米麹は、みりんの甘みや風味を作り出すために欠かせないものです。米麹の酵素がもち米のでんぷんを糖分に変えます。
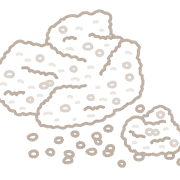
焼酎またはアルコール: アルコールは、発酵を抑えて風味を調整するために使用されます。また、アルコールは保存性を高める役割も果たします。

※現在は、みりんを飲用ではなく調味料として使うことが多いため、うま味を加えるためや品質の安定化を目的として、ブドウ糖や水あめ、コハク酸、乳酸、グルタミン酸ナトリウムなどが添加される場合もあります。
みりんの製造工程
製造工程は、伝統的な方法で行われる場合の手順です。
みりんの製造方法は日本酒に似ていますが、仕込み水の代わりに焼酎や醸造アルコールを使うのが特徴です。
醸造に使われる麹菌は、日本酒や醤油と同じ黄麹菌で、麹のよしあしがみりんの品質に影響を与えます。
「本みりん」の製造過程に基づいています。
1、原料の準備
みりんの原料であるもち米、米麹、そして焼酎または醸造アルコールを用意します。
焼酎またはアルコール: もち米と米麹が発酵しすぎるのを防ぎ、また保存性を高めるために使われます。
もち米: 高品質なもち米が使用されます。もち米は、みりんに必要な甘みと旨みを作り出す重要な材料です。
米麹: 米を蒸して米麹菌を加えたものです。酵素の働きにより、もち米のでんぷんを糖に分解する役割があります。
2、もち米の蒸し
もち米を洗浄し、水に浸してから蒸します。もち米を蒸すことで、発酵しやすい状態にします。
3、原料の混合
蒸したもち米に米麹を混ぜ、そこに焼酎またはアルコールを加えます。この段階で原料が一緒に仕込まれます。アルコールの働きにより、もち米の発酵が抑えられつつ、酵素による糖化が進んでいきます。
4、発酵と熟成
原料を混ぜた後、発酵と熟成の工程に入ります。通常、半年から1年程度、タンクの中でじっくりと熟成させます。この間に、米麹の酵素がもち米のでんぷんを糖に変換し、みりんの甘みやコクが生まれます。
- 発酵中、アルコールがもち米や米麹からの旨味成分を引き出し、みりん特有の風味が作られます。
5、圧搾
発酵・熟成が終わったら、圧搾して液体を搾り出します。この段階で、みりんのベースとなる液体が完成します。
6、濾過(ろ過)
搾り出したみりんを濾過(ろか)し、不要な固形物や不純物を取り除きます。これにより、みりんの透明度が高くなり、味わいが整えられます。
7、加熱殺菌
最終段階では、みりんを加熱して殺菌します。この工程で発酵が止まり、保存性が向上します。
8、瓶詰め
殺菌が終わったら、みりんを瓶詰めし、完成品として出荷されます。
まとめ

- 原料の準備 → 蒸し → 混合 → 発酵・熟成 → 圧搾 → 濾過 → 加熱殺菌 → 瓶詰め
このような工程があり、甘みと深い風味を持った本みりんが作られます。みりん風調味料の場合は、工程や原料が異なる場合があり、糖類や香料を使用して短期間で作られることが多いです。
みりんの成分・機能
みりんの成分とその機能は、日本料理に非常に重要な役割を果たします。
糖分
- 成分: みりんの甘みの元は、主にもち米のデンプンが米麹の酵素によって糖に変わることで生まれます。この糖分はグルコースやマルトース、オリゴ糖といった成分から構成されます。
- 機能:
- 甘味を加える: みりんは砂糖よりもまろやかな自然な甘みを持っており、料理に調和した甘さを加えます。これにより、煮物やタレなどが甘辛い味わいに仕上がります。
- 焦げ目を防ぐ: みりんの糖分は、加熱したときに焦げにくいため、料理に適度な焼き色と艶を与えながら、食材が過度に焦げるのを防ぎます。
アルコール
- 成分: 本みりんには約14%のアルコールが含まれています。みりん風調味料や発酵調味料は、アルコール度数が非常に低いか、ほとんど含まれていません。
- 機能:
- 照りを出す: 加熱時にアルコールが蒸発する際、食材に光沢を与え、料理に美しい照りを生み出します。これが「照り焼き」のような料理で特に重要です。
- 臭みを取る: アルコールは魚や肉の臭みを抑える効果があり、素材の風味を活かすために使われます。
- 浸透性を高める: アルコールが食材に染み込みやすくし、調味料の風味を食材全体に行き渡らせます。
有機酸(乳酸など)
- 成分: みりんには、発酵過程で生成される乳酸などの有機酸が含まれています。
- 機能:
- 旨味を引き出す: 有機酸は料理全体の味を調和させ、酸味を抑えつつも旨味を強化します。これにより、料理に深みのある風味が生まれます。
- 防腐効果: 有機酸は食材の保存期間を延ばす軽い防腐効果もあります。
アミノ酸
- 成分: もち米や米麹に含まれるたんぱく質が分解されて生じるアミノ酸(グルタミン酸など)が、みりんには豊富に含まれています。
- 機能:
- 旨味を強化: アミノ酸は、料理に自然な旨味を加えます。これにより、食材そのものの味をより引き立て、深みのある味わいを実現します。
- 調味料のバランスを整える: アミノ酸の存在により、みりんは甘みだけでなく、他の調味料との調和を取るため、味がバランスよく仕上がります。
水分
- 成分: みりんには約40%程度の水分が含まれています。
- 機能:
- 調和作用: みりんの水分は、他の調味料や味付けを均一に拡散させ、味のなじみを良くします。
- ツヤ出し: 水分が含まれていることで、加熱時に食材に均一にコーティングされ、照りやツヤを生み出します。
グリセリン(発酵に由来)
- 成分: グリセリンは、発酵の過程で生成される甘味成分で、粘度のあるテクスチャーを持ちます。
- 機能:
- 食材を柔らかくする: グリセリンは食材に吸着し、肉や魚を柔らかく仕上げる効果があります。
- 保湿効果: 料理の水分を保ち、ジューシーに仕上げる効果もあります。
みりんは、単なる甘味料ではなく、糖分、アルコール、有機酸、アミノ酸など多様な成分が複合的に作用し、以下のような効果を料理に与えます:
- 甘みと旨味のバランスを整える。
- 食材に照りとツヤを与える。
- 臭みを取り、風味を引き立てる。
- 食材を柔らかくし、保湿効果を高める。

これらの成分が、みりんを日本料理において欠かせない調味料にしています。
いかがでしたか?
みりんは甘味、酢は酸味ですがどちらも酒を原料としてプラス発酵の技術で製造されます。
身体に良く、大切な調味料の一つですね。
参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


