こんにちは、garesuです。
日本料理に欠かせない風味豊かな食材で、その美味しさは特有のうま味と香ばしさにあります。
鰹節のおいしさ
うま味の相乗効果
鰹節のうま味の成分は、鰹の魚肉に大量に含まれるイノシン酸です。
核酸(かくさん)の一種であるイノシン酸は生きている鰹の魚肉には存在しません。死んだ後に筋肉中のアデノシン三リン酸(ATP)という物質が分解することで生成されます。
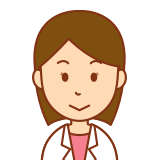
核酸とは‥遺伝子の材料となる物質のことです。
すべての生物に含まれており、細胞が生まれ変わるために必要です。
イノシン酸は鰹の死後硬直が解けた直後に最も増加するのでその時期に煮熟して酵素のはたらきを止めます。
止めることによりイノシン酸を多くふくむ鰹節をつくることができます。
カビ付けを施す前の荒節にも強いうま味があるのはこのためです。
カビ付けの工程でも、カビが分泌する酵素によってイノシン酸が増加してさらにうま味が増します。
一方で、カビはタンパク質分解酵素のプロテアーゼを出して鰹のタンパク質を分解してグルタミン酸などのアミノ酸を鰹節の中に蓄積していきます。
鰹節の旨みは、イノシン酸とグルタミン酸のうま味の相乗効果によって生まれるものなのです。
また、鰹節の上品な風味や香りもカビの働きによるものです。
カビはたくさんのリパーゼ(脂肪分解酵素)を出して、鰹の脂肪分を分解します。その際にアルコール類などの香気成分を生成して、魚の生臭さや燻煙のにおいを抑えて香りが高く、まろやかな鰹節の風味を作り出します。
健康効果
鰹節は日本の伝統的な食材で、栄養価が高く、健康に多くの効果があると言われています。
高タンパク質
鰹節は非常に高いタンパク質を含んでおり、100gあたり約70gものタンパク質が含まれています。タンパク質は、筋肉の維持・修復、免疫機能の向上、エネルギーの供給などに重要です。
DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)
鰹節にはDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などのオメガ3脂肪酸が含まれています。これらの脂肪酸は、脳の健康を保つことや心臓病のリスクを減少させる効果があります。また、炎症を抑える作用もあるとされています。
ビタミンとミネラル
鰹節は、ビタミンB群(特にB12)、鉄分、カリウム、リンなどのミネラルも豊富に含んでいます。ビタミンB12は神経系や血液の健康維持に重要で、鉄分は貧血予防に役立ちます。カリウムは血圧を調整し、心臓の健康に寄与します。
抗酸化作用
鰹節には抗酸化作用があり、老化や病気の原因となる活性酸素を減らす効果が期待されます。この抗酸化作用により、細胞のダメージを軽減し、生活習慣病の予防にも繋がる可能性があります。
消化促進
鰹節に含まれるイノシン酸やグルタミン酸などの旨味成分は、胃腸の働きを助け、消化を促進するとされています。消化不良や胃の不快感を和らげる効果が期待できます。
血行促進と疲労回復
鰹節に含まれる成分は血液の循環を良くし、体内の老廃物を効率よく排出する効果があるとされています。これにより、疲労回復や冷え性の改善にも役立つとされています。
鰹節は、タンパク質、DHA・EPA、ビタミンB群、ミネラルなどの栄養素が豊富で、心臓や脳の健康維持、抗酸化作用、消化促進など、さまざまな健康効果が期待できます。日常の食事に取り入れることで、健康維持に役立つ優れた食材です。
鰹出汁のとりかた
鰹だしのとり方は、シンプルですが、料理の味を引き立てるための基本的な作業です。
一番だしのとりかた
一般的な鰹だしのとりかたです。

材料
水:1リットル
鰹節:20〜30g
1 水を加熱する
鍋に水(1リットル)を入れ、中火で沸騰直前まで温めます。
沸騰させると鰹節の風味が損なわれるため、泡が出る寸前で止めるのがポイントです。
2 鰹節を加える
沸騰直前になったら火を止め、鰹節を一気に加えます。
鰹節が水に均等に広がるように軽くかき混ぜます。
3 静置する
鰹節を加えた後、そのまま1〜2分ほど置いて、鰹節が沈んでいくのを待ちます。
これにより、しっかりと旨味が抽出されます。
4 こす
鰹節が鍋の底に沈んだら、だしをこし布やキッチンペーパーを敷いたザルでこします。このとき、鰹節を強く絞らず、軽く押す程度にして、苦味が出ないようにします。
5 完成
こしただしを別の容器に移して、使用します。
ポイント
水の温度管理:沸騰させすぎないことが重要です。温度が高すぎると苦味や雑味が出てしまうため、90℃程度で鰹節を投入するのが理想です。
鰹節の量:だしの濃さは好みに合わせて調整できます。濃いだしをとりたい場合は、鰹節の量を増やします。
使用用途
みそ汁、うどんやそばのつゆ、お鍋のスープ、煮物など、幅広い和食料理に使えます。鰹だしは旨味のベースとして重要で、料理全体の味をまとめ上げる役割を果たします。
二番だしのとりかた
一番だしをとった後のだし殻でとるのが二番だしになります。
材料
一番だしを取った後の鰹節
水:1リットル(新しく用意)
1 一番だしを取った後の鰹節を再利用
一番だしを取った後の鰹節をそのまま鍋に残します。
鰹節にはまだある程度の旨味が残っているので、これを再利用します。
2 新しい水を加える
鍋に新たに1リットルの水を加えます。鰹節をこの水で再度煮出します。
3 加熱する
中火にかけて、ゆっくりと沸騰させます。
一番だしの時とは異なり、二番だしの場合は、軽く沸騰させて鰹節の残った旨味をしっかり引き出すことがポイントです。
4 煮出す
沸騰後、弱火にして3〜5分程度煮出します。煮出す時間が長いほど、だしの風味が濃くなりますが、強すぎる火力で煮詰めすぎると苦味が出ることもあるので注意が必要です。
5 こす
煮出し終わったら、鰹節をキッチンペーパーやこし布でこしてだしを取り出します。
絞り出す必要はなく、自然にこすだけで十分です。
6 完成
こしただしが「二番だし」です。一番だしと比べて風味が強く、やや濃厚な味わいとなります。
二番だしの用途
煮物や味噌汁など、味のしっかりした料理に適しています。
また、二番だしは鍋料理のスープや、うどん・そばのつゆのベースにも使えます。
一番だしが繊細で上品な料理向けであるのに対し、二番だしはしっかりした風味を必要とする料理に使うことが多いです。
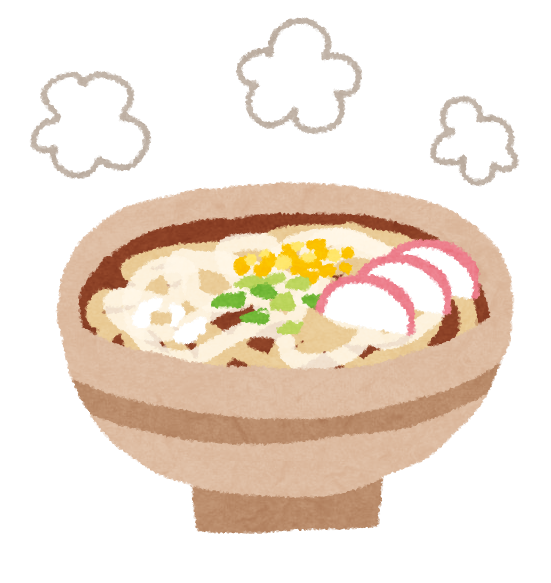
いかがでしたか?
鰹節だけで作る二番だしは、手軽で無駄なく食材を活用できる便利な方法です。風味が強い料理にうまく取り入れて、和食の味わいを深めてみてください。
また、残っただし柄を乾燥させてフードプロセッサーで細かくし、鰹粉を作って食卓で活用してみてはいかがですか?

参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


