こんにちは、garesuです。
ヨーグルトづくりに欠かせない乳酸菌は、動物の乳にふくまれる糖類を分解して乳酸を生み出す細菌の総称です。
もともと自然界に存在していて、乳糖などの糖類(ラクトール)などを栄養源にして繁殖して、その過程で生成される乳酸や酢酸によって乳中のタンパク質が固まり、ヨーグルトが出来上がります。
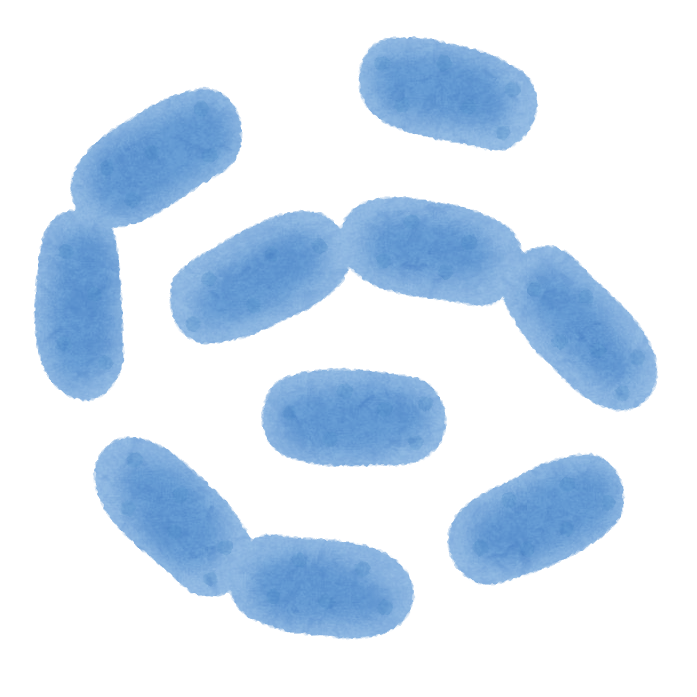
代表的な乳酸菌
乳酸菌にはさまざまな種類があります。
現在わかっているだけで数百種類に及ぶといわれています。
そのうち、ヨーグルトの種菌(たねきん)に使われる代表的な乳酸菌が、サーモフィラス菌とブルガリア菌です。
サーモフィラス菌
サーモフィラス菌の主な働き
- 乳糖を分解して乳酸を生成し、ヨーグルトの酸味を引き出す。
- タンパク質を凝固させ、ヨーグルトのクリーミーな質感を作る。
- 乳酸菌として、腸内環境を整え、腸内フローラのバランスを保つ効果が期待されます。
- 菌の形は球菌 生育が早く、繁殖の過程でブルガリア菌の生育に必要な蟻酸という物質を作り出します。
この菌は比較的温暖な環境で発酵が進むため、ヨーグルト作りには適した温度(約40~45℃)が必要です。
また、サーモフィラス菌はプロバイオティクスの一種としても注目されていて、腸内環境を改善する健康効果があるとされていますが、実際の効果は個人差があるため、一定の研究が続けられています。
ブルガリア菌
ブルガリア菌の主な働き
- 乳糖を分解して乳酸を生成し、ヨーグルトの酸味を強めます。
- サーモフィラス菌と共生的な作用を持ち、相互に助け合うことで発酵がよりスムーズに進行します。具体的には、ブルガリア菌が生成するアミノ酸がサーモフィラス菌の成長を促し、サーモフィラス菌が生成する酸がブルガリア菌の成長を助けます。
- 乳酸の生成により、牛乳のタンパク質が凝固し、ヨーグルトのクリーミーでなめらかな質感を生み出します。
- 菌の形は細長い桿菌 繁殖の過程でサーモフィラス菌の生育に必要なアミノ酸やペプチドをつくりだします。
保健機能を高める乳酸菌
保健機能を高める乳酸菌には、腸内環境を整えたり、免疫力を向上させたりするさまざまな効果が期待されています。
ビフィズス菌(Bifidobacterium)
- 特徴: ビフィズス菌は、大腸に生息する善玉菌の代表格で、腸内環境を改善する働きがあります。乳酸だけでなく酢酸も生成し、腸内のpHを酸性に保つことで悪玉菌の繁殖を抑えます。
- 健康効果:
- 腸内環境の改善
- 便秘の予防・改善
- 免疫力の向上
LGG乳酸菌(Lactobacillus rhamnosus GG)
- 特徴: 世界的に広く研究されている乳酸菌で、腸内での定着力が強いことが知られています。また、ストレスや生活習慣の乱れによる腸内フローラのバランスを整える働きがあります。
- 健康効果:
- 腸内環境の改善
- 免疫力の向上
- アレルギー反応の抑制効果が示唆されています。
ラクトバチルス・カゼイ・シロタ株(Lactobacillus casei Shirota)
- 特徴: ヤクルトに使用されている有名な乳酸菌で、腸内の悪玉菌を減少させ、腸内環境を整える効果があります。胃酸や胆汁にも強く、生きたまま腸まで届くことが特徴です。
- 健康効果:
- 腸内フローラの改善
- 便秘や下痢の予防
- 免疫力をサポート
L-92乳酸菌(Lactobacillus acidophilus L-92)
- 特徴: アレルギーに対する効果が注目されている乳酸菌です。花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を和らげる働きが期待されています。
- 健康効果:
- アレルギー症状の軽減
- 免疫機能の調整
ガセリ菌(Lactobacillus gasseri)
- 特徴: 体脂肪の低減に寄与するとされる乳酸菌で、内臓脂肪を減らす効果が一部研究で確認されています。また、腸内に長く留まる能力も高いとされています。
- 健康効果:
- 体脂肪の減少
- 腸内環境の改善
- メタボリックシンドロームの予防
プラントラム菌(Lactobacillus plantarum)
- 特徴: 主に植物由来の乳酸菌で、腸内に長く生き残ることができ、消化吸収を助ける働きがあります。特に野菜や漬物などに含まれています。
- 健康効果:
- 消化促進
- 免疫調整
- 抗酸化作用
フェカリス菌(Enterococcus faecalis)
- 特徴: 非常に小さく高い免疫賦活作用があり、免疫力を高める働きがあることで知られています。この菌は生菌ではなく死菌として摂取されることが多く、それでも強い効果を発揮します。
- 健康効果:
- 免疫力の向上
- 風邪予防やインフルエンザ予防
乳酸菌を含む食品
- ヨーグルト
- 発酵乳飲料(ヤクルトなど)
- チーズやバター
- 味噌、漬物、キムチなどの発酵食品
ヨーグルトの健康効果
ヨーグルトの栄養成分
ヨーグルトには、良質なタンパク質やビタミンB2、カルシウムが豊富に含まれています。
また、増結作用の高いビタミンB群の複合体である葉酸もたくさん含まれています。
しかも、牛乳のタンパク質は発酵の過程でアミノ酸に分解されて消化吸収がよくなるため、牛乳よりも効率的に摂取することができます。
同じように、カルシウムは乳酸と結び付いて乳酸カルシウムとなって、腸から吸収されやすくなります。
牛乳に含まれる乳糖は普通、腸内の乳糖分解酵素「ラクターゼ」によって分解されます。
しかし、腸内のラクターゼが少ないと、お腹がゆるくなる場合があります。このような症状を乳糖不耐症といいます。欧米人に比べて日本人はその割合が多いといわれています。
ヨーグルトの乳酸菌は、ラクターゼを作り出して乳糖を分解するので、乳糖不耐症の人でも安心して食べられます。
腸内環境の改善
ヨーグルトは、腸内環境の改善に非常に効果的な食品として広く知られています。ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を整え、消化機能の改善や便通の向上に役立ちます。
ヨーグルトが腸内環境を改善する仕組み
- 善玉菌の補給
ヨーグルトには、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が含まれています。これらの菌は腸に到達して増殖し、腸内の有害な悪玉菌を抑制します。善玉菌が多い腸内では、発酵が活発に行われ、腸の動きがスムーズになるため、便秘や下痢などの消化不良を予防・改善することが期待できます。 - 乳酸の生成
乳酸菌は腸内で乳糖を分解して乳酸を生成します。乳酸は腸内を弱酸性に保つことで、有害な細菌や悪玉菌の繁殖を抑制し、腸内の健康を保つ手助けをします。これにより、腸内環境が整い、健康に良い状態が維持されます。 - 短鎖脂肪酸の生成
ビフィズス菌などの一部の腸内細菌は、食物繊維などを分解して短鎖脂肪酸を生成します。短鎖脂肪酸は腸の細胞のエネルギー源となり、腸粘膜を保護し、炎症を抑える効果があります。また、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進し、便通を改善する効果もあります。 - 有害物質の抑制
悪玉菌が増えると、有害なガスや物質(アンモニアやインドールなど)が生成され、腸内環境が悪化します。しかし、ヨーグルトに含まれる善玉菌がこれらの悪玉菌の繁殖を抑えるため、有害物質の生成も減少し、腸内環境が改善されます。
ヨーグルトを摂取することで期待できる健康効果
- 便秘の予防・改善
ヨーグルトを摂取することで、腸内の乳酸菌やビフィズス菌が増加し、腸内の水分を引き込んで便を柔らかくし、腸の動きを活発にするため、便秘が改善されやすくなります。 - 下痢の改善
ヨーグルトに含まれる善玉菌が腸内フローラを整えることで、腸内での有害菌の活動を抑制し、下痢の症状も緩和されることがあります。また、抗生物質の使用後に乱れがちな腸内バランスを整える効果も期待されます。 - 免疫力の向上
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、全身の免疫機能に大きな影響を与えます。腸内環境が整うことで、免疫細胞の活動が活発になり、体全体の免疫力が向上する可能性があります。これにより、風邪やインフルエンザなどの感染症への抵抗力が強まります。 - 体重管理やメタボリックシンドロームの予防
善玉菌が腸内で短鎖脂肪酸を生成すると、脂肪の蓄積を抑える働きが促進され、体重管理やメタボリックシンドロームの予防に役立つことが研究で示されています。特にガセリ菌やビフィズス菌がこれらの効果に寄与するとされています。 - アレルギーの抑制
一部の乳酸菌(例えばL-92乳酸菌)は、免疫機能を調整することで、アレルギー症状を緩和する効果があるとされています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの症状を抑える効果が報告されています。
ヨーグルトは、腸内環境の改善に非常に効果的な食品として広く知られています。ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)を整え、消化機能の改善や便通の向上に役立ちます。以下に、ヨーグルトが腸内環境を改善するメカニズムやその健康効果について詳しく説明します。
ヨーグルトが腸内環境を改善する仕組み
- 善玉菌の補給
ヨーグルトには、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が含まれています。これらの菌は腸に到達して増殖し、腸内の有害な悪玉菌を抑制します。善玉菌が多い腸内では、発酵が活発に行われ、腸の動きがスムーズになるため、便秘や下痢などの消化不良を予防・改善することが期待できます。 - 乳酸の生成
乳酸菌は腸内で乳糖を分解して乳酸を生成します。乳酸は腸内を弱酸性に保つことで、有害な細菌や悪玉菌の繁殖を抑制し、腸内の健康を保つ手助けをします。これにより、腸内環境が整い、健康に良い状態が維持されます。 - 短鎖脂肪酸の生成
ビフィズス菌などの一部の腸内細菌は、食物繊維などを分解して短鎖脂肪酸を生成します。短鎖脂肪酸は腸の細胞のエネルギー源となり、腸粘膜を保護し、炎症を抑える効果があります。また、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進し、便通を改善する効果もあります。
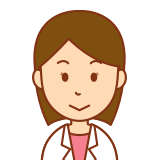
短鎖脂肪酸とは‥主に腸内の細菌が食物繊維などを発酵することで生成される脂肪酸の一種です。
4.有害物質の抑制
悪玉菌が増えると、有害なガスや物質(アンモニアやインドールなど)が生成され、腸内環境が悪化します。しかし、ヨーグルトに含まれる善玉菌がこれらの悪玉菌の繁殖を抑えるため、有害物質の生成も減少し、腸内環境が改善されます。
ヨーグルトを摂取することで期待できる健康効果
- 便秘の予防・改善
ヨーグルトを摂取することで、腸内の乳酸菌やビフィズス菌が増加し、腸内の水分を引き込んで便を柔らかくし、腸の動きを活発にするため、便秘が改善されやすくなります。 - 下痢の改善
ヨーグルトに含まれる善玉菌が腸内フローラを整えることで、腸内での有害菌の活動を抑制し、下痢の症状も緩和されることがあります。また、抗生物質の使用後に乱れがちな腸内バランスを整える効果も期待されます。 - 免疫力の向上
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、全身の免疫機能に大きな影響を与えます。腸内環境が整うことで、免疫細胞の活動が活発になり、体全体の免疫力が向上する可能性があります。これにより、風邪やインフルエンザなどの感染症への抵抗力が強まります。 - 体重管理やメタボリックシンドロームの予防
善玉菌が腸内で短鎖脂肪酸を生成すると、脂肪の蓄積を抑える働きが促進され、体重管理やメタボリックシンドロームの予防に役立つことが研究で示されています。特にガセリ菌やビフィズス菌がこれらの効果に寄与するとされています。 - アレルギーの抑制
一部の乳酸菌(例えばL-92乳酸菌)は、免疫機能を調整することで、アレルギー症状を緩和する効果があるとされています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの症状を抑える効果が報告されています。
腸内環境を改善するためのヨーグルトの摂取方法
- 継続的な摂取: ヨーグルトの効果は、1回の摂取ではなく、毎日継続して摂ることで得られます。毎日100g~200g程度のヨーグルトを食べることが推奨されています。
- 無糖ヨーグルト: 糖分の多い加糖ヨーグルトよりも、無糖のプレーンヨーグルトを選ぶと、余計な糖分を摂取せずに健康効果を得られます。甘味が欲しい場合は、フルーツや蜂蜜を少量加えることで自然な甘さを楽しむことができます。
- 空腹時の摂取: ヨーグルトの乳酸菌は酸に弱いため、胃酸の分泌が少ない空腹時に摂取する方が、より多くの乳酸菌が腸まで届きやすくなります。
ヨーグルトに含まれる乳酸菌の例
- ブルガリア菌(Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
- サーモフィラス菌(Streptococcus thermophilus)
- ビフィズス菌(Bifidobacterium)
- ガセリ菌(Lactobacillus gasseri)
- LGG乳酸菌(Lactobacillus rhamnosus GG)
- ラクトバチルス・カゼイ・シロタ株(Lactobacillus casei Shirota)
これらの菌は、腸内環境を整えるのに重要な役割を果たします。
いかがでしたか?
ヨーグルトは腸内環境を改善するのに優れた食品であり、継続して摂取することで、便秘の改善や免疫力向上など、さまざまな健康効果が期待できます。
毎日の食生活に無糖のプレーンヨーグルトを取り入れることで、腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラを整える習慣をつけると良いでしょうね。

参考文献
「発酵食品ソムリエ講座テキスト1 伝統的な和食と日本の発酵文化」U-CAN
「発酵食品ソムリエ講座テキスト2 世界にひろがる発酵食品と健康」U-CAN
「発酵食品を楽しむ教科書」 ナツメ社


